
生子渕<加園>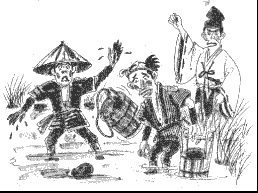 「なんだやこの石、へんちくりんな形だな。その上いくつも穴ぼこがあいてんぞ。」 「気味わりい石だな、その穴ぼこの奥に、何かもぐっていねえかや。」 みんなは、石をかこんでガヤガヤと勝手なことを言い合った。そのうちにとしよりのひとりがその石の泥をよく荒いおとしてみると、石は青っぽくて艶がありその上、 七つも穴があいていた。 としよりは、だまってその石を眺めていたが、急に思い出したように話しはじめた。 「あのなあ・・・、今から五・六年前だったと思うけどなあ。この沼のあたりで赤ん坊をだいた若い女の人がうずくまっていたんだよ。その女の人は毎年石裂参りにきていたらしく、 この土地の様子に詳しいようだった。 でもなあ、おれがなにを聞いても黙っていて、しまいには逃げるようにしてあの草むらん中へはいっちまったんだよ。」 「ほんじゃそら、その女が赤ん坊をこの沼に捨てたんじゃねえかや。」 「すると、あの声は赤ん坊の泣き声か?」 「それじゃ、この石は・・・・。」 若者たちは気味悪そうに言った。 「まあ、いずれにしても、この石を供養してみんべじゃねえか。」 と、としよりは言った。そのことばに村人たちも、 「そうすることがよかんべ。とにかく宝蔵院に持って行って供養してもらうことにすんべえ。」 と言って、さっそく供養してもらった。 そののち、村人たちが金を出し合って、お地蔵様を作らせ、沼の底から出て来た青くて穴のあいている石をお地蔵様にだかせてお堂に安置した。すると「オボコ、オボコ」 という不思議な音はぷっつりと聞こえなくなった。 それから、この沼のあたりを「生子渕」と言うようになり、この集落の人たちは、今でも毎年11月23日にはお堂の前に集って供養を続けている。 この内容は、鹿沼市玉田町にお住まいの黒川フミさんが「続子どものための鹿沼のむかし話」の中で、まとめられたものです。 |