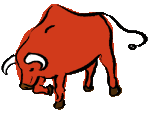| 2010〜2007 |
||||
| NO 14 2010 |
高内壮介 「古代幻想と自然」 より * 生命は無目的な行動の中に、目的以上の目的を、神よりも正確に察知してゆく。 それが進化である。 * 進化とは、生命という自動制御系による無目的運動による目的の獲得に他ならない。 * あらゆる時代の変革は遊び現象から始まる。 * 遊びとは、生命が生命の進化の道を基準系無しに、遊びそのものの中から基準系を作り出してゆく、 操作の体系である。 |
|||
| NO 13 |
* 彌生も末の七日、明ぼのヽ空朧々として、月は有明にて光をさまれるものから,不二の峰かすかに見えて、上野谷中の花の梢、又いつかはと心細し。むつまじき限りは宵よりつどひて船に乗りて送る。千住と云ふ所にて船をあがれば、前途三千里の思ひ胸にふさがりて、幻の巷に離別の涙をそゝぐ。 行く春や鳥啼き魚の目はなみだ (元禄二年) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2010・10・15 記 かの有名な「奥の細道」の初めの方にでている離別の句である。なんともはや、筆舌尽くしがたきしなやかさと、鍛え抜かれた名詩文であろうか。鳥は啼き魚は目に涙を浮かべて行く春を悲しんでいるということだが、自分を送ってきてくれた人たちと、いよいよ別れる時だという芭蕉の満腔の思いを、鳥の啼き声や魚の目の涙に託して吐き出したものである。対象に依拠して然も対象を超越したこの表現法は、近代象徴詩法をも超えているといえる。 (参考 半田良平「芭蕉俳句新釋」) |
|||
| NO 12 |
* 縄文の「天空への螺旋上昇吊り上げられ運動」は、いわば人間の中の死者の、 さらには死者と合体した神の運動である。たとえ、縄文の作品にむかいあったにしたところで おのれのなかに、死者を持たない人、少しも神を思ったことのない人には、 この運動は決して感受できないであろう。 * 塔とは、宇宙の奥へむかって突きささってゆく、祈りの結晶である。 * 円空と木喰上人の木彫仏は、いずれも修験道美術、すなわち、 縄文の伏流水の江戸時代になっての噴出である。 |
|||
| NO 11 |
(音楽と永遠)より もう美しいだけでは駄目なのだ。 心の琴線にふれる しんみりした抒情の深みに感傷するだけでは、 もう音楽は駄目なのである。 復活すべきは、美ではなく、生命それ自身である。 もし、音楽が永遠と出会う一会があるとすれば、 それは自我の表現でも、 自己存在の証としての音楽でもなく、 歴史の深層に沈んだ神々の在りかを、 魂振りによってよみがえらせ、 古代の記憶を想起させることなのである。 想起は創造以上の創造行為である。 今、創造ということが、やたらに叫ばれているが、 真の創造とは、イマジストになることではなく、 億年の経過を想起することなのだ。 そして、それは同時に、 始原への始触でもあったのだ。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
不勉強で大変もうしわけないと思う。鹿沼出身の歴程派詩人・哲学者で、 文芸・科学評論家でもあった高内壮介氏を再発見できた。 この詩の中の「音楽」という言葉を、「現代の詩」に変えてみても、 まったくその通りなのだと思う。人間がいま文明の修羅場にあって 生きる不安をどうすることもできずに混迷しているからであろうと思う。 |
|||
| NO 10 |
* 春 ゆらぐつり橋手に手をとりて 渡る井田川 オワラ 春の風 * 夏 富山あたりかあの燈火は 飛んでゆきたや オワラ 灯とり虫 * 秋 八尾坂道わかれて来れば 露か時雨か オワラ はらはらと * 冬 若しや来るかと窓押しあけて 見れば立山 オワラ 雪ばかり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2010/9/4 記 2010年9月3日、書家 柿沼翠流氏の呼びかけで書泉会の方々と、 富山市八尾、「おわら風の盆」を見に行ってきた。その際に詠んだ歌3首。 * 翠流も雨情もここに時雨れたり 八尾の衆の風の盆歌 守城 * 彼の岸にしなる手先はとどきたり 井田の川面のゆらぐぼんぼり 守城 * 立山に風送られて鎮まりし 色づく八尾おんな盆唄 守城 |
|||
| NO 9 |
* 木枯らしを馬上ににらむ男かな 良寛 * 凩の果てはありけり海の音 言水 * 凩の吹きゆくうしろすがたかな 嵐雪 * 木がらしや目刺にのこる海のいろ 芥川龍之介 * 海に出て木枯らし帰るところなし 山口誓子 * 木枯らしや百舌の速贄残しけり 守城 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ * 濁り河にごれるままに水脈なして 海にそそげり海ひろきかな 「黎明」 十月会誌 * 暁ちかみ かなかなのなく 声きゝつ いま一時を 寝らくたぬしも 「野づかさ」 * たはやすく 雲のあつまる 秋空を みなみに渡る 群鳥のこゑ 「幸木」 * 若きらが親に先立ち去ぬる世を 幾世し積まば國は栄えむ 「幸木」 |
|||
| NO 8 |
* 暗く暑く大群衆と花火待つ * おそるべき君等の乳房夏来る * 水枕ガバリと寒い海がある 半田良平 * 鶏頭の花に差しくる日のひかり 吾も浴みつつ傍らに立つ (歌集 幸木)より * この土の下にねむれるわが子らと 墓ならべむは幾とせの後 (歌集 野づかさ)より |
|||
| NO 7 |
* すでに障害のない景色のなかにいる精神 明日を案内するように大きな夕陽が深潜してくる 「白菜」より * 秋日の海岸は誰もいない わき腹を波に洗わせながら 私は波音をきいている 一時間二時間 流木のままでいると それはざっざっと飽きながらの繰り返しに聞こえてくる 私の海への帰休はまだまだ先のように思えてくる 「帰休」より * ある日 その双眸は私の生の残留を強烈に照射してきた 昨日まで海の波音は羊水の音律であったのに それは 海への回帰はまだ先のことと断定してくる 残留は残留ではない 余計余分でもない ましてや付録ではない いつしか双眸には柔和なくぐもりが生まれてきて それを培養してくれる 私の精神はいま満潮にある 「残留」より |
|||
| NO 6 |
冬牡丹の花 人が死ぬと 暖かいところでは 蝶になるといわれている 寒いところでは井守になると口伝えられている 穏やかなところでは 蜩になると信じられている しかし 誰れとも挨拶しないで 急に他界してしまったあなたには 冬牡丹の花になって来てほしい 質素で気品高い紅色の花になって来てほしい そして藁の傘のなかから子供たちを 静かに眺めていてほしい |
|||
| NO 5 |
* あな哀れ 我が詩情は詩とならずして絵画となるなり * 芸が身を助くる程のふしあわせ * 我ハ市井ノ陋巷ニ住ヒシテ 人工ヲ愛ス 人工ハ愛シキ哉 人工ハ悲シキ哉 人工ハ寂シキ哉 我ハ永遠ヲ信ゼズ 人工モマタ亡ブベシ 亡ブモノハ命ヲ持テり 命アルモノハ年老イテ朽ツルナリ 我ハ俗ノ俗 俗極マレバ 仙トナルベシ 我ハ我ガ人工ノ藝術ニ羽化登仙シ 忽チ堕落シテ俗ニ落ツ マタヨキ哉 斯クシテ我ガ頭髪ニ霜ヲオキ 眉毛長ク延ビ行ク也 昭和21年4月24日手稿 より |
|||
| NO 4 |
「生物と無生物の間」「ロハスの思考」「できそこないの男たち」などより *** 1987年、母親のものだけが子どもに伝えられるミトコンドリアDNAの研究によって、全人類共通の太母が30万年くらい前に、アフリカに住んでいたひとりの”イヴ”だったことがわかった。 *** 自然界は渦巻きの文様にあふれている。 巻貝・蛇・蝶の口吻・植物のつる・水流・海潮・気流・台風の目・銀河系自体 etc *** 渦巻きはおそらく生命と自然の循環性をシンボライズする意匠なのだ。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 茂木健一郎 (「吉本隆明のDNA」・・藤生京子著)より *** ぼくは「底抜けのニヒリズムを突き抜けていったところに、限りなく明るい生命哲学がある」と考える。 |
|||
| NO 3 |
* 20世紀の「母達」はどこにいるのか。寂しい所、歩いたもののない、歩かれぬ道はどこにあるのか。現代の基本的テエマが発酵し発芽する暗く温かい深部はどこであろうか。そここそ詩人の座標の「原点」ではないか。 * 「段々降りてゆく」よりほかないのだ。飛躍は主観的には生まれない。下部へ、下部へ、根へ、根へ、花咲かぬ処へ、暗黒のみちる所へ、そこに万有の母がある。存在の原点がある。初発のエネルギーがある。メフィストにとってさえそれは「異端の民」だ。そこは「別の地獄」だ。一気にはいけぬ。 * 私達は未来に向けて書いているのではなく、未来へ進む現在へ向けて書くのだ。偶像を排撃せよ!観念的労働者主義をうちやぶれ!今日の大地の自らの足もとの深部を描け!汝、足下の大地を描くか。 |
|||
| NO 2 |
* ぼくは倫理性のない思想を尊重することができない。 * ぼくは批評家を胎内にもたない芸術家を好まない。 * 現代における真の詩人は必然的に反詩人的である。 * 現代の現実の危機的な様相をまえにして詩人が歌ったり音韻に乗じたりすることに抵抗を感じているとすれば、それは詩人が無意識のうちに現実の批評の構造を感知しているが故である。斯かる詩人の生み出す詩に期待せねばならない。 * 日本の現代詩は詩の美学について伝統を持っていない。もし伝統として拠るべき処を求めるならば、新古今集を以って終了した短詩型の伝統的美学に拠る外はない。しかも現代詩は正しくこの美学に反逆することによってしか存在の理由を持たない。 笑いし母の通夜に雪ふる 船村 徹 * あわ雪の中に顕(た)ちたる三千大千世界(みちおほち) またその中に沫雪(あわゆき)ぞ降る 良寛 * 生死(しょうじ)の中の雪降りしきる 山頭火 |
|||
| NO 1 2010 |
ドストエフスキー 「作家の日記」1877年7・8月号より * 「カラマーゾフの兄弟」を通して経験し、取り戻さなくてはならないのは、自分たちの魂のなかにあるこの「大地」なのだと思うのです。いや、翻って考えるなら、大地と一体になった身体、自らの傲慢さを捨て、土のぬくもりと生きたやさしさのなかにすっぽりと溶け合わせることのできる身体ー。そして、そのときこそ「何か確固としてゆるぎないもの」は、確実に一人ひとりの魂の中に降りてくると、ドストエフスキーは語りかけているように思えてならないのです。もしもこの恍惚の体験が,アリョーシャひとりに限られるものであるとしたら、この大地がすべての人間の魂の奥底にひそみ、すべての人間が踏みしめている同じ大地があるという信念を、一人ひとりに与えることができなかったならば「カラマーゾフの兄弟」が時代を超えていつまでも、読み継がれることがなかったでしょう。 亀山郁夫 「新訳カラマーゾフの兄弟」を読む・NHKブックス・・より * 「はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒の麦のままである。死ねば多くの実を結ぶ。」 ヨハネの福音書第12章24節 |
|||
| NO 12 2009 |
まことひとびと 索むるは 青きGossan 銅の脈 わが求むるは まことのことば 雨の中なる 真言なり (筆録) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Question * おそれおおくも、「雨の中なる」のところ、「雪の中なる」としたいものだが?(良寛・山頭火の詩に連帯して) * Gossan=出羽三山のうちの「月山」のことか? * なお、「和歌即真言・・西行」の言葉あり。 |
|||
| NO 11 |
Tertiary the younger tertiary the younger Tertiary the younger mud-stone あおじろ日破れ あおじろ日破れ あおじろ日破れに おれのかげ Tertiary the younger tertiary the younger Tertiary the younger mud-stone なみはあおざめ 支流はそそぎ たしかにここは 修羅のなぎさ ** Tertiary the younger mud-stone 第三紀新生泥岩層 北上川の西岸にロンドンあたりの地質と似た水辺がある。 賢治が農学校の生徒たちと遊んだところという。 |
|||
| NO 10 |
自分の手で表札をかけるに限る。 精神の在り場所も ハタから表札をかけられてはならない 石垣りん それでよい。 石垣りん 「表札」より |
|||
| NO 9 |
・・・・・・ 戦いが敗れたとき きみはすでに勝者だったから 敗れたものが勝つことのないたたかいをはじめているやさしさが視えない 村々の幻影を噛みつぶして父が死んだとき 視えないたたかいの遺伝子が ぼくのなかを流れたのが視えない・・・・・ 「瞑り」 より ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 血を失った透明な風土の峡で 静かに乳岩を噛んで恐怖の音楽を聞いた 神のようにあっけなく燃えつきてしまった数枚の憎悪 もう出発する星座もないので天体望遠鏡を捨てた どうして板切れ一枚の思想となって 大洋が窒息するまで航行しつづけないのか 一壜の思考を使い果たした夜 銀河も涸れた 針のように燃えて舌は幻野を駆けめぐる 昆虫たちの執着もなく波に洗われる泥人形よ 拡散する八月の粒子よ 溶ける男よ 「溶ける男」 より |
|||
| NO 8 |
「動物哀歌」より 象が落日のようにたおれたという その便りをくれた人もいなくなった 落日とありふれた陽が沈むことの 天と地ほどのへだたりのような 深い思いをのこして それから私は何処でもひとり ひとりのうすれ日の森林をのぼり ひとりのひもじい荒野をさまよい ひとりの夕闇の砂浜を歩き ひとりの血の汗の夜をねむり ひとりで恐ろしい死の世界へ 入っていくよりほかはない 前足から永遠に向かうようにたおれたという 巨大な落日の象をもとめて |
|||
| NO 7 |
一本の樹にも 流れている血がある 樹の中では血は立ったまま眠っている * 書くことは速度でしかなかった 追い抜かれたものだけが紙の上に存在した * 読むことは悔悟でしかなかった 王国はまだまだ遠いのだ |
|||
| NO 6 |
夏になれば また 蝉がなく 花火が 記憶の中で フリーズしている 遠い国は おぼろだが 宇宙は鼻の先 なんという恩寵 人は死ねる そしてという 接続詞だけを 残して |
|||
| NO 5 |
永遠となる 言葉は熟れきったとき 沈黙する 果実は熟れきったとき 地に帰る 死を 熟れきった生として とらえること 谷川俊太郎 「詩と死をむすぶもの」より |
|||
| NO 4 |
一生がもう終わるのに、言い切れぬ事がたくさんあるのに 何を話してもいいのだと、心のどもりを解き放とう。 「序詩 どもり」より ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 止まっていないこと、 それで私の書く平凡なことでも 川の流れのように 足を洗ったり手を洗ったりできるでしょう。 「止まるな」より |
|||
| NO 3 |
詩人とは、誰よりも正直な人でなければならない。 人間の精神について、自分の存在について、誰よりも 正直に語るために、嘘をまなぶ。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ まっすぐに流れる河はない 抵抗なしに進む考えはない 悲しめるもの 骨を曲げて眠れよ |
|||
| NO 2 |
ぼくはでてゆく 冬の圧力の真むこうへ ひとりっきりでは耐えられないから たくさんのひとと手をつなぐというのは嘘だから ひとりっきりで抗争できないから たくさんのひとと手をつなぐというのは卑怯だから ぼくはでてゆく ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ぼくの孤独はほとんど極限に耐えられる ぼくの肉体はほとんど過酷に耐えられる ぼくがたおれたらひとつの直接性がたおれる もたれあうことをきらった反抗がたおれる |
|||
| NO 1 2009 |
|
|||
| NO 12 2008 |
「戦後代表詩選」 詩の森文庫 より 戦争が終わったとき パパイアの木の上には 白い小さな雲が浮いていた 戦いに負けた人間であるという点で 僕等はお互いを軽蔑しきっていた それでも 戦いに負けた人間であるという点で 僕等はちょっぴりお互いを哀れんでいた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 引き上げ船がついたところで 僕等は めいめいに切り放たれた運命を 帽子のようにかるがると振って別れた |
|||
| NO 11 | 「戦後代表詩選」 詩の森文庫 より おれはずぶ濡れの悔恨をすてて とおい航海にでよう 背負い袋のようにおまえをひっかついで 航海に出ようとおもった ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 街は死んでいる さわやかな朝の風が 頸輪ずれしたおれの咽喉につめたい剃刀ををあてる おれには掘割のそばに立っている人影が 胸をえぐられ 永遠に吠えることのない狼に見えてくる 「繋船ホテルの朝の歌」より 歌う者のいない咽喉と 主権者のいない胸との 血をはく空洞におちてくる にんげんの悲しみによごれた夕陽をすてにゆこう この曠野のはてるまで ・・・どこまでもぼくは行こう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 勝利を信じないぼくは どうして敗北を信じることができようか おお だから 誰もぼくを許そうとするな 「兵士の歌」より |
|||
| NO 10 | あざらしの夫婦が並んで死んだ 永い旅から帰ってきたら 何の腐爛も起さずに 雌は立派に立ったままで 眼から氷柱を垂らしていた 犬が食ってしまったらしい雄は 赤い泥のような小さな塊りになり クレバス沿いに点々と並び 一番新しいらしいのが 一本湯気を立てていた 詩集「南極」より |
|||
| NO 9 | いかぶねはかなし、花開かない海の向日葵 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ いかは うみに瞬くはるをうたひ 死の苦しみを 冷笑した かなしみは世の美しさと ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ いかよ 南海の孤島には きみの甲羅が卒塔婆をたてる! ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ いかよ きみは海のそこの夢がすきだ 待つことはつらいこと 未来は現在と同じことだ と 幾たびきみに呼びかけても きみは・・・・きみは・・・・ ああ 香料の湯ぶねにひたりきり 笑いながら死んでゆく海のエピキュリアンよ |
|||
| NO 8 |
|
|||
| NO 7 |
|
|||
| NO 6 |
|
|||
| NO 5 |
|
|||
| NO 4 | 魔法の国で、子どもらは夢を見ながら 眠っている、過ぎ去る日々のかたわらで、 眠っている,ほろび去る夏のかたわらで ながれをただよいくだりながらーー 金いろのひかりのなかにためらいながらーー いのちとは、夢でなければ、なんなのだろう? |
|||
| NO 3 |
|
|||
| NO 2 | ひかりのにがさ また青さ 四月の気層の光の底を 唾しはぎしりゆききする おれは一人の修羅なのだ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ まことのことばはうしなわれ 雲はちぎれてそらをとぶ ああかがやきの四月の底を はぎしり燃えてゆききする おれはひとりの修羅なのだ |
|||
| NO 1 2008 |
謹 賀 新 年 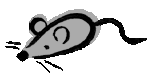 2008 2008
|
|||
| NO 14 2007 |
いかりのにがさまた青さ 四月の気層のひかりの底を 唾し はぎしりゆききする おれはひとりの修羅なのだ |
|||
| NO 13 | たれか謂ふわが詩を詩と わが詩はこれ詩にあらず わが詩の詩にあらざるを知って 始めてともに詩を言うべし 良寛 |
|||
| NO 12 |
東京のマンションからの夜景10月6日(孫の運動会の日に上京)撮影 |
|||
| NO 11 | 生をたわわに 実らせることによってしか わたしは死を熟させることができない *** 人間は ついにさびしいのだ 土に わが身を返済しなければ 土へのオード より 新川和江 |
|||
| NO 10 |
|
|||
| NO 9 | わたしのなかにいつも流れるつめたいあなた 純粋とはこの世でひとつの病気です 愛を併発してそれは重くなる 吉原幸子「オンディーヌ抄」より |
|||
| NO 8 | 母 あゝ麗はしい距離(デスタンス) 常に遠のいてゆく風景・・・・・・ 悲しみの彼方、 母への 捜り打つ夜半の最弱音(ピアニシモ)
|
|||
| NO 7 | その前で立ち尽くすだけでは生きていけない それがどんなに美しかろうとも 谷川俊太郎 |
|||
| NO 6 | 考えること これが科学の茎 最後になぞがとける これが科学の花 朝永振一郎 ノーベル賞物理学者 |
|||
| NO 5 | *人生で成功していく、幸せな人生を送ろうと思ったら、 人に対して感謝の気持ちを持つことだ。 山下泰裕 |
|||
| NO 4 | パリの舗石をはぐと その下は砂浜だ 砂浜は海へ通じるだろう 政治は通りで行われる 寺山修司 「落書学」より |
|||
| NO 3 | わたしが一番きれいだったとき わたしの国は戦争で負けた そんな馬鹿なことってあるものか ブラウスの腕をまくり卑屈な町をのし歩いた 茨木のり子「わたしが一番きれいだったとき」より |
|||
| NO 2 | 自分は果たして今、憧れの熱意に燃えて飛ぶ矢であるだろうか 齋藤 孝 「教育力」より |
|||
| NO 1 2007 |
 2007・元旦・初日の出 市花木センター 去年今年 貫く棒の如きもの 高浜虚子 |
|||