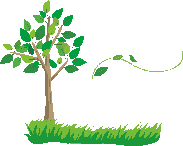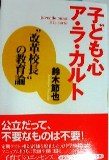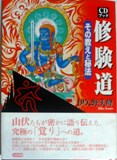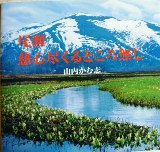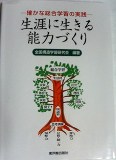| 2010/ 12/18 |
�P�@�u���̍��A���̎����v�@�����@�@���t�V�� �Q�@�u�I�R�̘̐b�v�@�����S�i�@���z�� �R�@�u�ߓ����l���W�v�@�ߓ����l�@1958/12/10���s �@�@�@�i�s���}���ق��؏o���j �S�@�u�팩�P�g���W�v�@�팩�P�g�@ �@�@�P�X�U�U�N�v���Ёu��{�팩�P�g���W�v���A�C���^�[�l�b�g�ɂ� �T�@�u�H���v�@�Z�p���v��W�@�s���}���ق��@�@���a�U�R�N�V���P�O�����s �U�@�u���тƁv�@�z�앐�j��W�@�s���}���ق�� �����T�N�R�����s �V�@�u�R�v�@�����m��W�@�s���}���ق�� �@�@�����P�O�N�T�����s �W�@�u�������Ȃ��Łv�@�ēc�g���@�V�� �@�@�����̏������W�@���ق̃x�X�g�Z���[�A�V�O���� �X�@�p���@ �@�@�u�ʐ^�o��̂����߁v�@�X������@�������� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/ 11/24 |
�P�@�u�������{���v�@�@���߁@�X�J�C�h�A �Q�@�u�ʐ^�o��̂����߁v�@�X������@�������� �R�@�u�Ñ㌶�z�Ǝ��R�v�@�����s��@�H��� �@�@�ꕶ���瓒��G���܂� �����{�l�̎��R�ςɂ͓ꕶ�́u�֊��Ƃ��Ă̎��R�v�A �퐶�E�Õ�����́u�M��Ƃ��Ă̎��R�v�Ƃ������҂Ƃ��Ă̎��R�ς��������B ���l���̎��R�ς͌Ñ�ȗ��̕s�C���ȑ��Ҋ��𑠂��Ȃ���A ���̌�͕��w�Ƃ������j�̕\�w�̌���邱�ƂȂ����j�̐[�w�ɖY���ꂽ�C���҂̓���A �\�̓���ʂ��ė��j�̒n�����ƂȂ��ė���Ă������B ������l���ƐԐl�ɂ͑��Ҋ��ƈ�̊��̎O���H������A �Ԑl�̈�̊��͐V�Í��̏ے��I���R��`����₪�Ĕm�Ԃɂ܂ŐS���B���̓���[�߂Ă������ƂɂȂ�A����́A�l���I�B�肭�̎��R����A�Ԑl�I���������R�ւ̕ϊ����Ӗ����Ă����B �E�E�E���̈�̊��͂����P��N��ʂ��āA���{�I�����̗ތ^���`��邱�ƂɂȂ�B NOTE�@�@�@�@2010/11/7�@�L �����̏��̒��ŁA��R�́u�l���ƐԐl�v �E�E�E���R�̑��Ҋ��ƈ�̊��̊�H�E�E�E�͓��{�����_�Ƃ��č����]�������ׂ����̂Ǝv���B ���Ɂu�l���`���Ɖ���̍��v�͖{���̖��������j�ɂ����ĉ���I�ȘJ��ł���Ǝv���B ���������l�E�v�z�ƁE���������҂������͔y�o���Ă����̂��B �S�@�u����}�����ւ̕����v�@�@�O�c�a�j�@�|�b�g�o�� �@�@����}�����͂ǂ��֍s���̂��I�H �T�@�p�� �@�@�u�����s�̕������v �U�@�p�� �@�@�u���ʂ܂̗��j�v�@�����s�j���y�Ł@�����s�j�Ҏ[�ψ��� �V�@�@�p�� �@�@�u�������̕���v�@�����ɂ��@�Q�O�P�O�D�W�D�Q�S �@�@�������H��c�� �W�@�p�� �@�u�Ȗ،��ߑ㕶�w�S�W�v�T�@���W�E�Z�̏W�E�o��W�E����W�@ �@�@����V���� �X�@����J��L�O���i�k���s�j�@�@�K��P�O�E�Q�X �@�@�u����J������@�J��v�@���a�P�Q�O�N���W����R���@�錴�J��� �P�O�@��錧�V�S�L�O�܉Y���p���@�K��P�O�E�Q�X �@�@�@�u���R�앗�W�@�v��R�O�N�v�@ �P�P�@�f��@�u���Ȏq�v�@�P�P�E�T �@�@�@���K���x�@���̕���@�F�s�{�q�J���� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/ 10/15 |
�P�@�u���̓ꕶ���p�ӏ܁v�@�@���߁@�V���I���@�i�����}���فj ���@���{�l�̃��[�c�͓ꕶ�l�ł���B���E�ɗނ�₷��|�p�Ƃ��Ă̓ꕶ�̓Ǝ����A ���͌������i���͊w�j�ƗD�����i�×͊w�j���̒��S�Ƃ���ȉ~�^���ɂ���ƌ���B ����ɂ́A���̑ȉ~�^���̈����N����<�V��ւ̗����㏸�݂�グ���^�����ɂ���ƌ���B �����ł����Ă����A���{�l�̖��������n���i���[�c�j�ł��肤��ƍl����B ���@�ꕶ�̋L�����̂ĂĊD�ƂȂ����A�吳�E���a�̓��{�̓��k�ɁA���Ƃ��A �{���E�����u���E���Ɏ��E����S���Ȃǂ�����B���ꂱ���A ���͉����ꕶ�l�̑h��ł͂Ȃ������낤���B �Q�@�u�m�Ԕo��V�ׁv�@���c�Ǖ��@�吳�P�S�N�R�����s�@�i�s���}���فj �R�@�u�s���̎������w�ҁ@����ȎO�v�@�����`�Y �@�@���ʂܗ��j�ƕ����@�����s�j�����I�v�@NO�V�@�Q�O�O�Q�D�R �S�@�u��t�ȎO�̐��U�ƍ�i�v�@����Î��@ �@�@���ʂܗ��j�ƕ����@�����s�j�����I�v�@NO 6�@�Q�O�O�P�D�R �T�@�u���D�E�y���[�̐��E�v�@��㐟���@���a�P�P�T���N�L�O���W �@�@�@�g�c�����Y�̍��D�فE��㐟���R���N�V���� �@�@�@�����s����㐟�����p�� �U�@�p�� �@�@�u�����I�o��S�I�v�@���J��D�@�@�u�k�� �V�@�p�� �@�@���W�@�u���C�~�v�@�R�{�\�l���@�@��镶�w��� �W�@�p�� �@�@�u���ʂ܂̗��j�v�@�����s�j���y�Ł@�����s�j�Ҏ[�ψ��� �X�@�p�� �@�@�u�������̕���v�@�����ɂ��@�Q�O�P�O�D�W�D�Q�S �@�@�������H��c�� �P�O�@�p�� �@�u�Ȗ،��ߑ㕶�w�S�W�v�T�@���W�E�Z�̏W�E�o��W�E����W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/ 10/2 |
�P�@�u�����ƍ��ׁ@����G���_�v�@�����s��@�H��� �Q�@�u���{���@�ꕶ�̌n���v�@�@���߁@�V���I�� �R�@�u���̐�㎍�v�@���іҗY�@�����O���[�v �@�@���`�I�Ȍ����d�T�O�N�j�@19997/12���s �S�@�u�̐l�@���c�Ǖ��̐��U�ƍ�i�v�@����Î��@�i��e�j �@�@���ʂܗ��j�ƕ����@�����s�j�����I�v�@�Q�O�O�S�D�R �T�@�p�� �@�@�u�����I�o��S�I�v�@���J��D�@�@�u�k�� �U�@�p�� �@�@���W�@�u���C�~�v�@�R�{�\�l���@�@��镶�w��� �V�@�p�� �@�@�u���ʂ܂̗��j�v�@�����s�j���y�Ł@�����s�j�Ҏ[�ψ��� �W�@�p�� �@�@�u�������̕���v�@�����ɂ��@�Q�O�P�O�D�W�D�Q�S�@�@�������H��c�� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/ 9/14 |
�P�@�u���l�ƕ����Ƃ̏C����v�@�����s��@�������X �Q�@���W�@�u���C�~�v�@�R�{�\�l���@�@��镶�w��� �R�@�u�z�������v�@�@�x�R�����w�z�����������ۑ��� �S�@�u���̖~���́v�@�������@���@�V������ ���{���\���閯�w�Ɨx��A�x�R�s�������́u����畗�̖~�v��ɂ�����l�̗��������B ��i�̓W�J�ɔo��E�Z�́E���w�������Ɏg���Ă���B�������������Ƃǂ߂�B ���@��߂ɂ݂��l�̂��Ƃ�֕��u�炭�@�@�v�ۓc�����Y ���@�Ⴕ�◈�邩�Ƒ������J���Č���Η��R�@�I�����@����� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����l�G�@�������� ���@���Η������Δ߂������Ƃ〈�ށ@�@�@�@�x�@���� �@�@�@���̍s�����̒Ⴓ�⍡���̏H �@�@�@�s���H����Ȃ��ɂ͂܂��a�̓� ���@�N��V���s�����̉��ς��ȁ@�@�@�@�@�@�{�� ���@�����҂��R�͂敗�̖~�@�@�@�@�@�@�щ� ���@���b�̓��ɓ��ɐ܂�ė��ꂯ��@�@�@�@�@茍X �T�@�p�� �@�@�u�����I�o��S�I�v�@���J��D�@�@�u�k�� �@�@�����s���@�u���l�ƕ����Ƃ̏C����v��� �@�@ �@�@�i���y�Ɖi���j���
���|�E�Ȋw�]�_�Ƃł������������s����Ĕ����ł����B �@���̎��̒��́u���y�v�Ƃ������t���A�u����̎��v�ɕς��Ă݂Ă��A �܂��������̒ʂ�Ȃ̂��Ǝv���B�l�Ԃ����ܕ����̏C����ɂ����� ������s�����ǂ����邱�Ƃ��ł����ɍ������Ă��邩��ł��낤�Ǝv���B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/ 9/4 |
�P�@�u��̖݁v�@�ΎR�Ћg�@�E�E�E�Љ��`�҂̈�e��W�E�E�E �@�@�@�ΎR�Ћg��e�W�ҏW�ψ��� �Q�@�u�Ȗ̓��b�v�@���{�������w�ҋ���@���u���I�o�� �R�@�u����̉̕��v�@�n�ӊ��Y�@���앶�Ɂ@�Ȃ̗t���[ �S�@�u��ˎ����̋�������v�@�A�B�@�W�p�Е��� �@�@�P�@�V�n�n���@�Q�@�\�^�@�R�@�C�G�X�̒a�� �T�@�p�� �@�@�u��㐟���@���̂Ɣʼn�̐��E�v�@�����s����㐟�����p�� �U�@�p�� �@�@�u�����I�o��S�I�v�@���J��D�@�@�u�k���@
�x�R�s�����A�u����畗�̖~�v�����ɍs���Ă����B���̍ۂɉr�̂R��B ���@�������J��������Ɏ��J�ꂽ��@�����̏O�̕��̖~�� ���@�ނ݂̊ɂ��Ȃ���͂Ƃǂ�����@��c�̐�ʂ̂�炮�ڂ�ڂ� ���@���R�ɕ������Ē��܂肵�@�F�Â���������Ȗ~�S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/ 8/26 |
�P�@�u���l�̍s���v�@���c���Y�@�R�E�z�l�̉� �@�@�@�Ȗ،����㎍�l�ɂ��āE�E�E���_�E�G�b�Z�C�W �Q�@�u�����v�@�Ё@���c�T���@�ďC �R�@�u���c�Ǖ��̉̂Ɛ��U�v�@�����L�O�Y���@�Z�̐V���Ё@�i�s���}���ّݏo�j �S�@ �p�� �@�@�u��㐟���@���̂Ɣʼn�̐��E�v�@�����s����㐟�����p�� �T�@�p�� �@�@�u�ʎ�S�o�v�E�E�ǂށE�����E�����E�E�@�y���Z�E�@�����f�S�@������ �U�@�p�� �@�@�u�����I�o��S�I�v�@���J��D�@�@�u�k�� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/8/20 |
�P�@�u�����I�o��S�I�v�@���J��D�@�@�u�k�� �Q�@���W�u����v �R�{�\�l�� �R�@�u���ʂܕ����N��v�R�R�������Q�Q�N�@�����s�������� �S�@�p�� �@�@�u�ʎ�S�o�v�E�E�ǂށE�����E�����E�E�@�y���Z�E�@�����f�S�@������ �T�@�̏W�@�u�K�v�@���c�Ǖ��@�@�i�s���}���ّݏo�j �U�@�̏W�@�u��Â����v�@���c�Ǖ��@�i�s���}���يٓ��{���j �V�@�u�̐l�@�Ǖ��Ɋāv�@���c�Ǖ�������@�i�s���}���ّݏo�j �P�@�f��@�u�Ă�������v�@�F�s�{�q�J�����@�V�E�Q�Q �@�@�E�E�E�C�ƃT���S�Ə����Ȋ�ՁE�E�E �@�@�Q�@�u��]���O�Y�u����v�@�@�s�����Z���^�[��z�[���@�V�E�R�P �@�@�E�E�E�����邱�ƁE�{��ǂނ��ƁE�E�E�u�����v�w�� �R�@�u��㐟���@���̂Ɣʼn�̐��E�v�W�@ �@�@�V�E�������i�W�@�@�����s����㐟�����p�ف@�W�E�W �S�@�f��@�u�t�Ƃ̗��v�@�F�s�{�q�J�����@�W�E�P�O �@�ēE�r�{�E����@���ѐ��L�@����B��E���i����E���G���E���䂫��E���ьO �@�Q�O�P�O�E���{�E�E�E�E�����铹�A�����Ƃ���B�E�E�E �@���{�̉Ƒ������߂āA�����邱�Ƃ̑f���炵����T��l���^�́B
�����Q�O�N�X���P�O�����܂�A���a�Q�O�N�T���P�X�������i�T�W�S���j�A �F�s�{���w������̑���w�Z�i�݂��̌�A�����鍑��w�p���ȂɊw�B �F�����ォ��Z�́E���Ȃǂ̓��e���͂��߁A�㋞���Ă͌E�c���ƌ�F�����B �����������w�Z�p�ꋳ�t�߂�Ȃ���A�P�O����l�Ƃ��Ă������B �����̏W�u��Â����v�吳�W�N�i�R�R�j���s�A���a�Q�R�N��e�̏W�u�K�v�����s���ꂽ�B ���{�|�p�@��܁A��Z�E�����s���Óc���w�Z�̂ق��A�s���ɉ̔肪�S����B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/ 7/16 |
�@�ŋ߂�
�Ǐ��@�Q�O�P�O�E�V�E�P�U�@�L �P�@�p�� �@�@�u�o��ӏ�450�ԏ����v�@�����T�@���t�V���@ �Q�@�p�� �@�@�u�ʎ�S�o�v�E�E�ǂށE�����E�����E�E�@�y���Z�E�@�����f�S�@������ �R�@�u�������o�����v�@�����@�T�@���t�V�� �S�@���W�u�����v �R�{�\�l�� �T�@�u�l�G�̌��t�v�@�����T�@���w�� �U�@�u�Ȗ،����㎍�N�Ӂv�Q�O�P�O �@�ŋ߂̕��|�ӏ��@�Q�O�P�O�E�V�E�P�U�@�L �P�@�u�V���K�[���W�v�@�����Y�p��w���p�ف@�V/�P�P �@�@���V�A�E�A�o���M�����h�Ƃ̏o��E�E�E�������閲�ƑO�q�E�E�E �Q�@�u��۔h�ƃG�R�[���E�h�E�p���W�v�@���l���p�ف@�V/�P�R �R�@�����ȑ�U�ԁ��ߜƁ��@�`���C�R�t�X�L�[ �@�@�@�������[�E�Q���M�G�t�w���E�C�[���t�B���@�@philips �@Super�[HM-CD
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/7 |
�ŋ߂� �Ǐ��@�Q�O�P�O�E�V�E�U�@�L 1�@�R�{�\�l�� ���W�@�u�S�{���v�@ ���@��ɕ���������̒��ɂ����ā@���ɑc����̂Ԃ₫���h��@���Ƃ����k���q���A���Ă����@���̂Ȃ��퉹�@���ق̔@�ƂȂ�̑��ɂ��@�ɂ��ۂ�S�y�Ɂ@���E�̂��������Ɂ@�Ⴊ�~��Â��Ă����@�@�@�u�k���q�v��� �Q �@�u�q�ǂ��̎��v�@���m�@�ҁ@���t�V�� �R�@�u�o��ӏ�450�ԏ����v�@�����T�@���t�V�� �S�@�u���ʂƓ��{�l�v�@�쒆�L���E�h�i�ʁ@�p��ONE�e�[�}�Q�P �T�@�u�ʎ�S�o�v�E�E�ǂށE�����E�����E�E�@�y���Z�E�@�����f�S�@������ �ŋ߂̕��|�ӏ��@�Q�O�P�O�E�V�E�U�@�L �P�@�u���̂��̎R�́`���{�̐�U�v�@���V�L�@�ē�i �@�@�@���ʉ�@7��1���@�����s�����Z���^�[ �@�@�@��f��@8��19���i�j�@ �@�@�P�T�F�O�O�`�A�A�P�W�F�R�O�`�����s�����Z���^�[��z�[�� �@���@��茧������̎O���u����E���a�E�n���v�ɁA�����̑����𗝔O�Ƃ��Ē��� �[���Y�����̃h�L�������^���[�B �Q�@�u�Ǎ��̃��X�v�@�F�s�{�q�J�����@6��30���@�P�S�F�P�O�` �@�@����@������F�@�r�{�@������l�@�ē@�����o ���@�]���̈ڐA�ɒ��ނЂƂ�̈�t�̐M�O�A���̂��ւ̎^�� �R�@�uEternal Chopin�@�i���̃V���p���v�@�d�l�h�@Classics�@�b�c�@�P�E�Q �@�@�Q�O�O�����@�`�������������������@�d������������
���u���ʂƓ��{�l�v�@���āA�쒆�L��������ꎟ���R�����̎�����b�̂Ƃ��A���͐��������Ƃ��Ă��������Ƃ�����B�������ɒɂ݂�m��؋�����̐l���h�ێ琭���Ƃ��Ƃ��炽�߂Čh�������B�h�i�ʎ��͓}��c���̕���ł��ڂɂ����������Ƃ�����B ���u���̂��̎R�́`���{�̐�U�v���݂āA���{�̗��R�����ɂ͖���������A�@��N�����ׂ���]������Ǝv�����B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/6 |
�ŋ߂� �Ǐ��@�Q�O�P�O�E�U�E�U�@�L 1 ���W�@�u���@�ԁv�@�R�{�\�l���@�@�������[ 2 �u���앨��v��ǂ݉����@�Έ䐳���@���}�АV�� �R�@�u�t�������{�l�_�v�@�{�V�Ўi�E���c�@���@�V���I�� ���@�g�̂��甭�����錾�t�ɂ́A����ɂӂ��킵������������B���̂��Ƃ̗������g�̂�������Ă���B�i���c���ɑ��āA�{�V�j ���@�����͕Ӌ����狻��B���J�[�`�i�ِ��E�ɐڂ���Ӌ������A�����Ƃ��C���^�[�i�V���i���ł���B�j ���@�����Ɏ�ƂȂ�Η����F�^�Ȃ�B�E�E�E�ՍϘ^ ���@�ދ��ȓ��X�̂����ɂ��������̖`��������ł���B�E�E�E���c ���@��l�ɂȂ���{�E�E�E�u�V�X�e���̘V���Ƒ�����̂ł͂Ȃ��A���n������Ƃ������Ƃ��v ���@���t�ɂ͗͂̂��錾�t�Ɨ͂̂Ȃ����t�������āA�͂̂��錾�t�ɐl�Ԃ͔�������B�͂̂��錾�t�������l�ɓ͂��B�����������t�̎����Ă���͈͂Ӗ��̃��x������Ȃ��āA�����ƃt�B�W�J���Ȃ��̂ł��B���t���g�������Ă��鋿���A�[�݁A���C�Ƃ������A��̓I�ȉ������g�̂̒��ɂ��݂���ł���B���c ���@�ǂ��ɗ������Ǝv������@��B�ꂪ�ʂ���������ǂ�ǂ�@��܂���B��������Ėx�܂���Ƃ��̒�ɂ����A�����ɂ����������Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ����܂��Ă���B�{�V �ŋ߂̕��|�ӏ��@�Q�O�P�O�E�U�E�U�@�L �P�@�u�א�Ƃ̎����v�W�@�������������� �@�@�@5��26���i���j�P�T�F�R�O�` �@�@�@��ʂ̉i���ɃR���N�V���� �Q�@�u���Ń����c���v�@�F�s�{�q�J���� �E�E�E�ߋ������n�߂�E�E�E�E1982�N�p���X�`�i���s�E�E�E�E�Ȃ����͊o���Ă��Ȃ��H �@�@�@6��1���@�P�W�F�R�O�`�Q�O�F�O�O �@�ēE�r�{�E����F�A���E�t�H���}���@�F�@�A�J�f�~�[�܊O���f��܃m�~�l�[�g�A�S�[���f���O���[�u�܍ŗD�G�O���f��ܑ��B�@�ē��炪���m�Ƃ��Čo���������o�m���푈���ނɁA�푈�̖{����`���Ռ��̃h�L�������^���[�E�A�j���[�V�����B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/5 | �ŋ߂� �Ǐ��@�Q�O�P�O�E�T�E�W�@�L 1 ���W�@�u���@�ԁv�@�R�{�\�l���@�@�������[ 2 �u�ǎj�]�H�v�@���c�K�v�@�W�����i���j �R�@�u�g�̂̕��w�j�v�@�{�V�Ўi�@�V���I�� �ŋ߂̖���E���y�ӏ��@�Q�O�P�O�E�T�E�S�@�L �P�@�u�����̎R�E�E�E�킽���̓ߐ{�v2006�N�@�R�����ގu�@�ďC�@�����j�N �@�@5���S���`6���ʐ^�W�@�Ȗ،����������Z���^�[ �Q�@�u�R�Ԏ��S�v�@1998�N�A �R�@�u���̕�X�v�@1998�N�A �S�@�u�����[���S�s����Ƃ��떳���v�@2002�N�@ NOTE �O�U�@ �R������͎������R��301�@�ɂ��Z�܂��̕��ł���B�R�x�ʐ^�̉�u������v�I�g����ANPO�@�l���{���R�A���ی싦�����A�����āA�ѓc��┎�ɁE�o���u�_��v������������ł���B����܂łɁu�R�Ԏ��S�v1998�N�A�u���̕�X�v1998�N�A�u�����[���S�s����Ƃ��떳���v2002�N�����s���Ă����B��������W�Ɏf���ʐ^�W����ɓ���đ�Ɍ��Ă���B����W�u�W��[�v1994�N�A��2��W�u�R���߁v2005�N���s���Ă��邪�A��W�͂��ꂩ��ǂ݂����Ǝv���Ă���B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/4 |
�ŋ߂� �Ǐ��@�Q�O�P�O�E�S�E�Q�U�@�L 1 �u�]�`�@��㐟���v�@���ї����@�@����V���Ё@�@�T�W�SP ���@��㐟���́u���Ă̕��v�́A�z�������ւ̏�M�z�̏o���_�Ƃ��A�{�b�e�B�`�G���́u���B�[�i�X�̒a���v�ɉ����č�i�̍\����W�J���A�����̎^���ɓ��B���悤�Ƃ����B����͉�ʂ̒���@���ʂ��镗�`�����悤�Ƃ���{�b�e�B�`�G���̈Ӑ}���������A����̕\���̒��S�ɐ�������㐟���̊�̊m������\�킷���̂ł��낤�B 2 �@�u��㐟��/���ƊG�̐��E�v�ҏW�@�����s����㐟�����p�� �@�@�����V���� 3�@�u��㐟�����`���������v�E�E�m�X�^���W�@�����߂āE�E �@�@�����s����㐟�����p�� 4�@�u��㐟���Ɩ��Y�v �E�E�E�_�c���i�E�ڑ��_��E�˓c�O�Y�E�����u���Ƌ��ɁE�E�E �@�@�����s����㐟�����p�� �T�@�u��㐟���[���킩�琶�܂����́[�g�ӂ̃f�U�C���v �@�@�J��15���N�L�O�@�����s����㐟�����p�� �U�@�u�Ȗ̐�㐟���v�[���̑��Ղ����ǂ�[ �@�@�J��15���N�L�O�@�����s����㐟�����p�� NOTE �T�@�@2010/5/8�@�L ��㐟���̎��Ɩؔʼn�ɐe����ł���B�f�p���Ɛ^�ʖڂ��A�����Ċ��m�������˔�������r�Ȋ����ɂ����āh�������l�h�������Ă�܂Ȃ����̂����Ԃ�ɂ������ɂȂ�A�\������Ă�������Ƃ����Ă͎���ɓ����邾�낤���B���ꂩ������Ɣʼn���Ȃ������ӏ܂��čs�������Ǝv���B �ŋ߂̖���E���y�ӏ��@�Q�O�P�O�E�S�E23�L �@�u���̗鉹�v�@�F�s�{�q�J�����@4/23�@�@�ē�i�@�C�E�`�����j���� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/4 |
�ŋ߂̖���E���y�ӏ��@�Q�O�P�O�E�S�E�X�@�L �P�@�u�����������l�v�@��heVisitor�@�F�s�{�q�J���� �@�@�ēE�r�{�F�g���E�}�b�J�[�V�[ �@�@�o���F���`���[�h�E�W�F���L���X�A�q�A���E�A�b�o�X �Q�@�u�����v�@�P�O�O�N��������j�@�F�s�{�q�J���� �@�@�ēF�f���N�E�`�E�@�r�{�F���C�E�Y�[ �@�@�剉�F�E�B���X�g���E�`���I �R�@��Z�^���q�@���@�C�I�������T�C�^�� �@�@�R�E�Q�W�����s�������Z���^�[ �S�@�u��Ȃ�ؖ��v�@�F�s�{�q�J�����@�@4/8 �@�@�ł���ɖ����Ă���̂́A�l�Ԃ��̂��̂ł���B �@�@�ēF�|���E�W���m �@�@�剉�F�L���E�w�W���A�E�H���r�� �ŋ߂� �Ǐ��@�Q�O�P�O�E�S�E13�@�L �P�@�R�{�\�l�����W�@�u���̏[���v�@�R�[���T�b�N�� �Q �R�{�\�l�����W�@�u�����v�@�R�[���T�b�N�� �R�@�u��㐟��/���ƊG�̐��E�v�ҏW�@�����s����㐟�����p�� �@�@�����V���� �S�@�u��㐟�����`���������v�E�E�m�X�^���W�@�����߂āE�E �@�@�����s����㐟�����p�� �T�@�u���w�̔��E���̔��v�@�c���g���@�Y�W �U ���W�u���̏��v�@�L�˒É����@�R�[���T�b�N�� �V�@�u�G���t�@���g���v�@�؊y�� �@�@���C�A���E���g�\���@�����L��E�����I�q�@�� �������ς܂��悤�A���R�͉̂Ɛ^���ɖ����Ă���B �@�@�E������g���q���Љ� �@�@�E�����̋V�� �@�@�E�ۂƌ~�A�ő�̓������琁i������g��M�j �@�@�E��������L���̓`�� �W�@�u���n�X�̎v�l�v�@�����L��@���@�\�g�R�g�V�� ���@LOHAS�E�E�ELifestyles Of Health And Sustainability NOTE �S�@�킽���͂��āA���̂悤�ɋL�������Ƃ��v���o�����B �@�@�@�@�@�@�@���L�̗����ɂ͐Ή��������N�̋��������� �@�@�@�@�@�@�@���m�̂��߂���������ȂɌ����J���� �@�@�@�@�@�@�@�����[�@���[�̓�@��]�̉Q �@�@�@�@�@�@�@�i���̃G�X�L�[�X�@�Q�X�j��� �X�@�u���y�̒������v�@���c�Ő��@���@�����V�� ���@���y�͌����Ă��ꎩ�̂ő��݂��Ă���̂ł͂Ȃ��A��ɓ���̗��j�E�Љ�琶�ݏo����A�����ē���̗��j�E�Љ�̒��Œ������B�ǂ�ȂɎ��R�ɉ��y���Ă������ł��A�������͕K�����炩�̕��������ɂ���ċK�肳�ꂽ�����������Ă���B�����āu���鉹�y���킩��Ȃ��v�Ƃ����P�[�X�̑唼�́A�ΏۂƂȂ鉹�y�Ƃ����瑤�́u�����g�v�Ƃ̐H���Ⴂ�ɋN�����Ă���悤�Ɏv���B�E�E�E���R�ɉ��y�����ƂȂǒN�ɂ��ł��Ȃ��B�������A�������g�̒������̕��ɂ��Ċ������o�I�ɂȂ邱�Ƃɂ���āA�����Ɗy�������y�ƕt���������Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����B �P�O�@�u���f�̎��l�@���e���O�Y�v�@�����G�� �@http://www7.ocn.ne.jp/�`hkasiwa./nisiwaki.htm ���Download |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/3 |
�ŋ߂� �Ǐ��E�ӏ܂Ȃ��@�Q�O�P�O�E�R�E�P�U�@�L �P �u���{�Ӌ��_�v�@���c�@���@�V���V���@���Q�T�R 2�@�u���_�����݂���v�@�J��@��@�u�k�Е��|���Ɂ@���Q�V�V�@�@�����V��� �R �u�u���v�Ƃ����v�z�v�@���R�@�߁@�V���I���@���Q�P�W �S�@�u�g�{������DNA�v�@�������q�@�����V���o�Ł@���Q�X�X �T�@�u�̏W�@���̂��̗��v�@�X�@�x�j�@�Z�̌����Ё@���Q�Q�W ��������ώ��̐X���炲���悢���������̏W�ł��B ��a�Ɠ����A�������͎��Â����Ȃ��炢�̂��̗��𑱂���X����ɐS����h�ӂ�\���܂��B NOTE 0�R�@�@2010/3/16�@ �Q�P���I�A���_�͗��R�ɂ���B�R�������A���R�Ƌ����������ɐ�����Ӌ��̖��ɂ���B�����ɒu���Y��Ă������N�̊�ő����������B�ł��ďo�ł�A���R�C�j�V�A�e�B�u�I�Ȃ����������ɁI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/2 |
�ŋ߂� �Ǐ��E�ӏ܂Ȃ��@�Q�O�P�O�E�Q�E�P�U�@�L NOTE 01 �@2010 /2/7 �킽���́u��̖���E��s���v�̒��ɑD���O�̎������������B�u��ӂ�v�͐����̂���݂ł���A�Đ��̌��i�݂Ȃ��Ɓj�ł���Ǝv����̂ł���B�E�E�E�E���{�̎��j�߂Ȃ���A�u��v�����ɂ��āA���̎���ƌI�����̂���悤��R�����A���Ր��ɒH��������Ǝv���Ă���B�ׂ͏d�߂��邪������̂͌v��m��Ȃ����낤�B NOTE�@�O�Q�@2010/2/16 ���킽���ɂƂ��Ă��A���̌�̐l�����K�肵���̂́A���̊w������̑S�����^���ł������Ƃ�����B�S�T�E�U�N�O�̂��̎������ǂ��߂��������A�ǂ������Ӗ����������Ƃ�����̂��B���̍ɂȂ�A�ł��邾���͂�����`�������Ǝv���B���̂��߂ɂ��g�{������J����������x�����Ȃ�ɓǂݒ������Ǝv���� �P �u�P�X�U�W�N�v�@�����G���@�@�����ܐV���@�R�O�OP ���@����͂U�W�N�ɋK�肳�ꂽ����ł���B��i���̓����������ۂƂ��āA�O���[�o���Y���̎�����J�����A�Q�O���I�B��̐��E�v���Ƃ�����B ���@�U�W�N��S�������E�̐V�����̑O��ł���u���X�^�[������`�v�́A�����v���ƃ\�A�M�̉�̂Ƃ����W�X�N�`�X�O�N�̎����ɂ���āA�{���̂��̂ɂȂ��Ă��܂����B�E�E�E�������̐��̕���E�E�E 2�@�u�v�z�Ƃ��Ă̑S��������v�@����C���@�@�����ܐV���@�Q�P�XP�@�ē� ���@���鎞���ʉ߂������Ƃ��A����ȍ~�̐��ɂƂ��Ăǂ������Ӗ��������Ă����̂��B�l�͎����̊��Ƃ��Ă̎��������Ԃ��Ƃ��ł��Ȃ��B ���@�O�h�I�Ȋw���^���ɋ������������Ă����ڂ��́A�A�t�����g�̕����ɏo���肷��悤�ɂȂ����B�t�����g�Ƃ����̂́A�Љ��`�w������̗��ŁA����Љ��`�ғ����i���Г��j�Ƃ����}�h�̊w���g�D�������B���Г��͓��{���Y�}����킩�ꂽ�A�\�����v�h�̓}�h�ŎO�h����́A�ǂ��炩�Ƃ����Ɠ��Ȑ��}�Ƃ����Ă����B�ڂ����t�����g�ɋ߂Â����̂́A���̓}�h���s���Љ�̌���������ԔF�����Ă���悤�Ɏv�������炾�B ���@���j�I�E�Љ�I�Ɍ����Ƃ��S�����Ƃ͂Ȃ����̂��B�ڂ��́u�Ӗ��̂�����v�Ƃ����\�����悭�g���B ���@�S�����^���́A�l�I�ȓ����ł���A���̐l���g�̐�������₤���������������B ���@�ߑ�I�m���̋\�Ԃ�ᔻ���A���吶�Ƃ����Љ�I�K�萫����́E���Ȕے肵�čĐ����悤�Ƃ���m���A���ꂪ�R�{�`���ɂ���đ�\���ꂽ���哬���̗��O�ł������B ���@�������E���ꐫ�E�����Ґ��E�Γ������d�������^���`�Ԃ������A�S�����̖{���Ȃ̂ł���B�V�O�N��ȍ~�̎s���^�������I�Ȋ����A���l�ւ̑ԓx�̂Ȃ��ɑS�����̓����͎p����Ă���ƍl����BIT�Z�p�̐i����������̐��E�őS�����I�Ȃ���̂̓l�b�g���[�N��ʂ��ĘA�����Ă䂭�\�������傫�������B �R �u�ł������Ȃ��̒j�����v�@�����L��@�@�����АV���@�Q�W�TP ���@�n�����a�������̂��S�U���N�O�A��������A�ŏ��̐������a������܂łɂ��悻�P�O���N���o�߂����B�����Đ���������Ă��炳��ɂP�O���N�A���̊Ԑ����̐��͒P��ŁA���ׂĂ����X�������B ���@�������̊�{�d�l������͏��ł���B�{�����ׂĂ̐����͂܂����X�Ƃ��Ĕ�������B���X�͑����ċ����c���ł���A�I�X�́A���̃��X�̌n�������X���n�����A�ׂ������̖������ʂ����A�h�g��������h�ɉ߂��Ȃ��B 4 �u�����m�[�g�v�@�g�{�����@�����Е��Ɂ@�T�U�UP 5 �@�u�g�{�����P�X�U�W�v�@�����@�@���}�АV���@�S�Q�RP 6 �u�߂Ɣ��m�[�g�v�@�T�R��v�@���}�АV���@�Q�X�RP 7 �u���m���o�l���v�@�֓��V��@�������i���j�E�E�E���M�Ǝ��Ɛ���ƁE�E�E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/1 |
�ŋ߂� �Ǐ��E�ӏ܂Ȃ��@�Q�O�P�O�E�P�E�P�@�L �P �u�{���_�v�@�g�{�����@�����Е��� 2�@�o �u�J���}�[�]�t�Z��v�̑��҂���z����p�@�T�R��v�@ �@�@�@�����АV�� �R �u�A�|�����̒n���v�@DVD�@�p�]���[�j�ē� �S �u��Ղ̋u�v�@DVD�@�p�]���[�j�ē� �T�@�u�����̂��ׂāv�@�@�Ђ낳����ďC�E�������j���@���{���|�� �U�@�u���I���t�v�E�E�����͂Ȃ������ɏh��̂��E�E �@�@�����L��@�؊y�� �V�@�ē��u�����Ɩ������Ƃ̊ԁv�@�����L��@�u�k�Ќ���V��  �މ�V�N �މ�V�N |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/12 |
�ŋߓǂ{�@�Q�O�O�X�E�P�Q�E�W�@�L �P �u�J���}�[�]�t�̌Z��v�@�P�E�Q�E�R�E�S���y�тT �i�G�s���[�O�y�ѕt�u�h�X�g�G�t�X�L�[�̐��U�v�u���E�E�����E�����̂͂��ꂩ�v�A�T�R��v�j �@�T�R��v�@��@�@�����ЌÓT�V�� ���@�u�͂����茾���Ă����B�ꗱ�̔��͒n�ɗ����Ď��ȂȂ���Έꗱ�̔��̂܂܂ł���B���˂Α����̎������ԁB�v���n�l�̕�������P�Q�͂Q�S�� ���@�w�����ォ��̔O�肾�������̒��ҏ������悤�₭�Ǘ������B�i�Q�O�O�X�E�P�P�E�P�P�`�P�Q�E�W�j����ɂ��Ă����̂�������i���B ���@���Z�E��w������̂���̋ꂵ�������l�X�Ȗ��ӎ�������Ƃ��ǂ����W�J���ɑh���Ă����B���w�I�Ȍ��̌��Ƃ��āA���̈Ӗ��������Ɛ[�߂Ă����������̂ł��� ���@��҂̋T�R��v���͉F�s�{���Z�̌�y�ŁA���ݓ����O�����w�̊w���߂Ă���B���N�A�����s�����ɍu���ɗ��Ă�������������A���߂Ă�����邱�Ƃ��ł����B�i�Q�O�O�W�E�P�O�E�P�j 2 �o�V��u�J���}�[�]�t�̌Z��v��ǂށp�@NHK�o�� �@�u���E���v�̐[�w �R�@�ēǁ@�u�h�X�g�G�t�X�L�[�@�@��Ɨ́v�@�T�R��v�@���t�V�� �S�@�u���̗́v�@�g�{�����@�V������ ���@��㌻�㎍�̎�������Ƃ��Č��o������i���B���炪�g�{���������I |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/11 |
�ŋߓǂ{�@�Q�O�O�X�E�P�P�E�W�@�L �P �u��N��v�@�����@�m�@�@��g�V�� �E�E�E�L���ɐ����邽�߂̒m�b�E�E�E�����̂Ȃ��W�����Ԃ̂��߂̃q���g���� ���@�Q�P�`�U�O�@�S�O�N�~�Q�O�O�O���ԁ��W�O�D�O�O�O���� �@�@�@�U�P�`�W�O�@�Q�O�N�~�i�P���P�P���ԁ~�R�U�T���j���W�O.�R�O�O���� �@�@�P���Q�S���ԁE�E�E�i�����E�H���E�����E�g�C���ȂǁA�P�R���ԁj�]�ɂP�P���� ���@������Ƃ������A�l�Ɖ���тɂ��ꂪ�Ō�Ƃ����C�����ŕt���������Ƃ��K�v�ɂȂ��Ă���B��̓s�x�A���݂��̍��ʎ����ƍl���Ă����������Ȃ��B�@ ���@�����炵���������邱�Ƃ����A�����͓�̎��Ƃ�����N�������e�n�Œz�������B��ԃ��j���[�ɂ�����邱�ƂȂ������̊S���ɓ˂��i�߂����B�����܂ł��A���Ȗ{�ʂ��т��C�ɗ����Ԃ邱�Ƃ�S�|�������B 2 �u���g���n���v�@�R�{�Lj�@�@�_�C�������h�� ���@�������͍���S�͂ő�Ɏ��g�Ƃ��Ă��A�Y�Ɗv���ȑO�Ɣ�ׂP.�W�� �̋C���㏸�͊o�傷�ׂ����B���B�̋C��^�[�Q�b�g�Q.���̊ϓ_���炷��ƁA�P.�W���Ƃ����̂͑����̊댯�����ł���B���ϋC�����Q���˔j����ƁA�n����ɗl�X�Ȕj�ǓI���ۂ�������B�Q���˔j���O�܂łɎ������͑��ݓ����ƔF�����ׂ����B�Ƃ���ƁA�Q�O�T�O�N�܂łɉ������ʃK�X�̍팸�ڕW�W�O���͓��R�ł���B ���@�ꍑ�̔ɉh�ƃT�X�e�i�r���e�B�i�����\���j�͂��̕�I������Ɗ��r�W�����Ɉˑ����邱�ƂɂȂ����B�Q�O���I�^�̑�ʐ��Y�E��ʏ���E��ʔp����O��Ƃ���H�ƕΏd�A�_�ƌy���́h�Ñ㕶���h�͑��ӕ����]�V�Ȃ�����邱�Ƃ͂P�O�O�p�[�Z���g�m���ł���B 3�@�u�S�]�R���g���[���Љ�v�@���X�z��@�@�����ܐV�� ���@����ƋC�Â���Ȃ��܂��A�l�����̕����ɗU������}�C���h�E�}�l�b�W�����g�B�]�Ȋw�̒m���������ꂽ�u�S�]�}�[�P�b�e�B���O�v�Ɋ�Â����̎�@�́C���⏤�i�L���݂̂Ȃ炸�A�����̐��E�ł��g���Ă���B�}�X���f�C�A��ʂ��ĂȂ���邱�̎�̐S�]����́A���������s�����̓�ґ���ɒP�������A�l���v�l��~�ւƒǂ����ށB�u�e���Ƃ̂��������v�������ău�b�V���������u���v�v������Ƃ��鏬�����A���̎�@��p���Đ��_�������B ���@�l�̔F�m��F���̂X�T���͖��ӎ��̕����ł�����B ���@���ӎ��Ɏ��Öْm�i�g�̉����ꂽ�F�m�j���ӎ��I�Ȓm�ɓ]������̂Ƀ��^�t�@�[���p������B �S�@�u�}�C���h�R���g���[���̋��|�v S�E�n�b�T���@�@�Ε��o�� �E�E�E Combatting Cult Mind Contorol�E�E�E ���@�}�C���h�R���g���[���̂S�̗v�f �@�P�@�s���R���g���[���E�E�E��ʎ҂ւ̕�E�A�E���A�s�����x�z�A�i���]�E�ˑ��j �@�Q�@�v�z�R���g���[���E�E�E�P���_�֑����I�������E���Ҍ� �@�R�@����R���g���[���E�E�E�߈����Ƌ��|���A�i�Ö��E�Î��E�W�c�S���j �@�S�@���R���g���[���E�E�E�O�������Ւf |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/9 |
�ŋߓǂ{�@�Q�O�O�X�E�X�E�P�Q�@�L �P �u�s�o�Z�Ƃ����������v�@���n�\�q�@NHK�u�b�N�X �E�E�E����̑��l���Ǝq�ǂ��̌����E�E�E 2 �u�n��ƂƂ��Ɋw�Z�����𗧂��グ��v�@�����w�@�����}�� �E�E�E���k�Ƌ��t�ƕی�ҁE�n�悪�Θb���Ȃ���w�т����A�炿�������ƂÂ���E�w�Z�Â���E�E�E�V���������s�쒆�w�Z 3�@�uCS�����|�[�gVo���@�U�R�v�@�[�ъ� �E�E�E���q�ǂ�����Ȃ��I�@���W�@���W�E�E�E �S�@�uCS�����|�[�g Vol �T�U�v �[�ъ� �E�E�E���q�ǂ�����Ȃ��I�@���W�@�����K���[�T�E�E�E ���Q�P���I�́u�m�̐��E�v���u�����\�ȊJ���v�Ɓu����v �@�@�����呍���@�g��O�V �T�@�u�����Ɩ������̂������v�����L��@�u�k�Ќ���V�� �U�@�u�����Ȃ����́v�@���c�M�j�@�V���� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/7 |
�ŋߓǂ{�@�Q�O�O�X�E7�E26�@�L �P �u���f�B�A�Ђ��ʼn���q�ǂ������v�@���N�ʐ^�V���� �@�@�E�E�E�E����P��E���C�T�������E�E�E 2 �u���t�ԓ`���v�@�����w�@������w��w�@�����@���w�� 3�@�u���t�����̒���v�@�����w�@������w��w�@�����@���w�ف@ �S�@�u�w�тƃP�A�ň�v�ďC�@�����w�@������w��w�@�����@���w�ف@ ���ґ�\�@�Î�@���A�����q �Q�O�O�X�E7�E2�@�L �P �u�w�Z���H�v�@�q���\�M�@��g�u�b�N���b�g�@NO �V�T�P 2 �u�����ƐH�v�@�����L��@�@��g�u�b�N���b�g�@NO �V�R�U 3�@�u�S���w�̓e�X�g�v�@�u���G�g�@��g�u�b�N���b�g�@NO�@�V�S�V �S�@�u�����]���v�@���J���F���@��g�u�b�N���b�g�@NO�@�V�T�Q �T�@�u�i���Љ�Ƌ�����v�v�@�@��g�u�b�N���b�g�@NO�@�V�Q�U �@�@���J���F�E�R����Y �U�@�u�����Ƌ����x��₤�v���ÍF���Y�@��g�u�b�N���b�gNO�@�V�T�R �V�@�u�����旧�a�c���̊w�Z���v�v���J���F����g�u�b�N���b�gNO�@�V�R�W �W�@�u�w�͂����߂钩�̓Ǐ��v�@�R�蔎�q�@���f�C�A�E�p�� �X�@�u���Ɍ������č炯�v�@���ÃL�����@��g�V���R�S�Q�@�P�X�W�U�N �E�E�E�ē��S���̐��U�E�E�E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/5 |
�ŋߓǂ{�@�Q�O�O�X�E�T�E�R�P�@�L �P �u�w�͂ƊK�w�v�@���J���F�@�����V���o�� 2 �u�w�͂̎Љ�w�v�@��g���X�@���J���F�E�u���G�g�� 3�@�u�w�͒ቺ�̎��ԁv�@��g�u�b�N���b�g�@NO�@�T�V�W �@�@���J���F�E�u���G�g�E�����r���E���c�T�q �S�@�u���Ǐp�v�@�����܃v���}�[�V���@�������� �T�@�u�����o�ώn�܂�v�@�������l�@�����V���o�� �U�@�u���E�v�T�����@��g���X �@�@���W�E�E�E���{�ŃO���[���j���[�f�B�[�� ���@�f��u������тƁv�ƐV�������̕����E�E �@�@�@�����i�i������w�E�@���w�����j�Ȃ� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/4 |
�ŋߓǂ{�@�Q�O�O�X�E4�E�Q�U�@�L �P �u�Ђ�߂��]�v�@�Ζ،���Y�@�V���V�� 2 �u���Ǝ����ނ��Ԃ��́v�@�J��r���Y�@VT�@���i�i �E�E�E���l�ƈ�t�̉������ȁE�E�E 3�@�u�����s�ҁv�@����O�F�@��g�V�� �E�E�E���ꂩ��̒E�E�E �S�@�u�������̓�������v���c�����@�O�w�o�ŁE���㓹���N�w�Q�O�u�E�E�E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/3 |
�@�ŋߓǂ{�@�Q�O�O�X�E�R�E�Q�Q�@�L �P �u�Z�͏W�E���@���ɐd��/�ʂ̉_�v�@ �@�@�i�����q�@���̐X���� 2 �u�Ƃ������D��v�@�������q�@���z�� �E�E�E����̗��j�Ɠ`����K�˂��E�E�E 3�@�u��O������v�@NO�P�V�@�i���j���{����Ȋw������ �E�E�E���W�F�w�Z�̏h���s���E�E�E �S�@�u�Ȗ،��ɂ����鍡��̎Љ��̂�����v �@�@�Ƃ������@�Љ��ɂ��n��Â���@ �E�E�E��Q�X���Ȗ،��Љ��ψ���c�@���\�@2008.7.4 �ŋߓǂ{�@�Q�O�O�X�E�R�E�P�@�L �P �u�Z�͏W�v�@���̂߂��Ă�/����锯�@ �@�@�i�����q�@���̐X���� 2 �u�Y�ޗ́v�@�I�����@�W�p�АV�� 3�@�u�w�Z�]���v�@���q��e�@�����ܐV�� �@�@�E�E�E��L�̃f�U�C���ƃc�[���E�E�E �S�@�u�����I�v�v�@�����P�W�E�P�X�E�Q�O�N�x �@�@�̌������W���C���g�v���O���������@�@�����s�����w�Z�E���w�Z |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/1 |
�ŋߓǂ{�@�Q�O�O�X�E1.�E�R�P�@�L �P �u���{�ň�Ԃ����w�Z�v�@��g���X�@���q��e �c���`�m��wSFC��w�@����E���f�B�A�����ȋ��� �E�E�E�n��A�g�̃C�m�x�[�V�����E�E�E 2 �u�R�~���j�e�B�E�X�N�[���\�z�v�@��g���X�@���q��e�E��؊��E�a�J���q�@ �E�E�E�w�Z��ϊv���邽�߂ɁE�E�E 3�@�uCS�����|�[�g�@Vol�@�U�Q�v�@���V�@���q�ǂ�����Ȃ��I�@ �E�E�E���ʊ��@���ʎx������i�Q�j�@�[�ъ� �S�@�u����\���I�v�@���̐X���Ɂ@�v���� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/12 |
�ŋߓǂ{�@�Q�O�O�W�E12.�E �Q�W�@�L �v [�w�͂���Ă�v�@�u���G�g���@��g�V�� �������w�Z�́A�������i����悤�Ƃ��Ă���u�s��v��u�I���v�Ƃ����������Ƃ͈قȂ錴���ɂ���Đl�X�̐V���ȎЉ�W���`�����Ă�����A�헪�n�_�ƂȂ肤��B������Ԃ����ɂ���l�X��,���܂��܂̉��ŏo�������ŁA�V�����l�ԊW�����сA���̋�����ʂ��āA�V���ȉ��l�Ȃ萬�ʕ��Ȃ�ݏo���Ă����B���̃v���Z�X�̒��Ő�������̂́A�q�ǂ������ł͂Ȃ��B���t���������A�����āA�n��̐l�X����������B �������w�Z�Ɋւ��āA�S�ʓI�Ȋw�Z�I���̎��R��F�߂�A�n��Љ�������A�����ƎE���Ƃ����Ȑl�ԊW���������Ȃ����̂ɂȂ��Ă��܂��͕̂K��ł���B ���w�͂̎��� �E�E�E�u���G�g�i����w��w�@�@�����j�@�u�w�͂���Ă�v��g�V���@���
2 �u�Ȃ����{�l�͊w�Ȃ��Ȃ����̂��v�@ �@�@�֓��F���@�u�k�Ќ���V���@�E�E�E�@���{�́u����́v�����߂��E�E�E ���@�w�Ԉӗ~�͖����ւ̊�]�ƕ\����̂ł���B ���@���{�l�ɖ��X�Ǝp����Ă����u�w�ԐS�̓`���v���������{�l�̍ő�̍��Y���B ���@�h�X�g�G�t�X�L�[�̑咷�ҁu�J���}�[�]�t�̌Z��v�̐V��i�T�R��v��j����j�\�����������Ȃ蔄��鍑�Ȃ�Ă���������̂���Ȃ��B����͐��E�Ɍւ���̊�Ղ��B 3�@�u�������w�Z�̒���v�@�u���G�g���@��g�u�b�N���b�g�@No�@611 �E�E�E�u�͂̂���w�Z�v�Ƃ͂Ȃɂ��E�E�E�E �S�@�u����̗́v�@���ϗ͖璘�@��g�u�b�N���b�g�@No�@715 �T�@�u����W���[�i���v�@2009�N�P�����@�w�� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/11 | �ŋߓǂ{�@�Q�O�O�W�E12.�E�R �L �v [�����w�Z�̒�́v�@�u���G�g�@�����ܐV�� �@�@�X�N�[���o�X���f���Etogether�� ���@�u�͂̂���w�Z�v�̂W�̗v�f �@�@�@�@�C�����̂���������E���W�c�iTeachers) �@�@�A�@�헪�I�ŏ_��Ȋw�Z�^�c�iOrganization�j �@�@�B�@�L���ȂȂ���ݏo�����k�w���iGuidance�j �@�@�C�@���ׂĂ̎q�ǂ��̊w�т��x����w�K�w���iEffective teaching�j �@�@�D�@�Ƃ��Ɉ�n��E�Z��ԘA�g�iTies�j �@�@�E�@�o�����I�ȉƒ�Ƃ̂������iHome-school link�j �@�@�F�@���S���Ċw�ׂ�w�Z���iEnvironment�j �@�@�G�@�O�����Ŋ����I�Ȋw�Z�����iRich school culture�j 2 �u����i�������{�𒾖v�������v�@���n�@���@�m��� ���@�~�܂�Ȃ�����i���̊g���B�E�E�E���������w�Z�̂V���ɏK�n�x�ʊw������������A�����̒�����эZ���ƃG���[�g�Z�����i��ł���B�{�g���A�b�v�^����v���g�b�v�^�ւƑǂ�������߁A���Ɍ�����ɂ������Ƃ������O�͂Ȃ��Ȃ����I���������Ƃ̋��瓊���͐�i���Œ�x���B�ƒ�̌o�ϗ͂╶���͂�����i���ɒ���������㉟��������{�́A�u�m�́v������������ɋt�s���Ă��邾���ł͂Ȃ��̂��I���@���烂�f���ł̓t�B�������h�ƃC�M���X�����˂��Ă���\�}�́A�Љ���`�ƐV���R��`�̎v�z�I�ȑΗ��ł�����B���{�̋���́A�ǂ�ǂ�V���R��`�Ɍ������Ă���B���_�Ƃ��Ă͕����������邱�ƂɊ뜜�̔O������l����������ǁA�킪�q�̂��ƂɂȂ�ƐV���R��`�I�Ȕ��f������l�������B�����ɂ��̖��̓��������B�P���ɂǂ��炩��I�Ԃ��Ƃ͂ł����A���̒��Ԃ����Ƃ��ǂ���ɂȂ邾�낤�B�E�E�E���łɌ�����́A��������������ߒ��ł͂Ȃ��A�s�������Œ肷��ߒ��ƂȂ��Ă���B 3�@�u�|�p�̐_�l���~��Ă���u�ԁv�@�@�@�Ζ،���Y�@������ �E�E�E�E�V�˂����̔]�͂ǂ����z���邩�E�E�E�E �@VT �E���c�N�@�E���X���@�E�R���m��@�E����u�̕�@�E�r��C�� ���@�������́A���������̓��Ȃ鑽�l���ɁA�����Ɩڂ��J�����ق����ǂ��̂ł͂Ȃ����B�E�E�E���������ӎ��̒��Ŋ�����l�X�ȃN�I���A�̑��l�����A���̂܂܁A�]�̒��̐_�o�זE�̃l�b�g���[�N�̑��l���ł�����B�E�E�E����̐��藧���ɂ����đ��l�ł���A�����āA�e�Ղɂ͗��������Ȃ��A�َ��ȑ��҂����e����B�E�E�E�l���Ƃ������l���̊C�̒��ŁE�E�E�E�@�Ζ،���Y �S�@�u�S�̔����v�@�ێR�@���@�@���w�كX�N�E�F�A �E�E�E�E���k������̃��b�Z�[�W�E�E�E�E ���@�J�E���Z���[�̎d���Ƃ́A�N���C�A���g�̘b����A�{�l���C�Â��ʏ����ȕω����������A���ዾ�Ŋg�債�āA���Ɋ�]�������Ă�����Ƃ��B �T�@�u�s���g�̗���Ɓv�@�t���������@���Ȃ����[ ���@��Ȃł����āA���̔��Ƃ���ƈႤ�Ƃ���Ƃ����̂́A�����ł��傤���B�`���̂��ߐ������ł��܂���A�����Ȉ֎q�ɍ��|���č������Ƃ߂Ă��܂��B�Ȃ��A�ޖx�ŋ��ނ��Ă���݂����ł��܂��Ȃ��B�u�k�Ŏg���ߑ��肸���ƃR���p�N�g�Ȃ��̂�O�ɂ����Ă�����ׂ肵�Ă���܂��B���̑�A����p�̑�Ƃ������ƂŁA���t���āu����v�ˁA�����l�[�~���O�ł���H�@�t�������� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/10 |
�ŋߓǂ{�@�Q�O�O�W�E�P�P�E�R�@�L �v [���s�s�Љ�Ɍ��t�̗͂��v�@�V���{�o�Ŏ� �E�E�E�i���Љ�͌��t�őގ�����I�@�@���X�z�� ���@�u���O�̑���͂�����ł������v �@�@�@�u�N�͂��̎d�������ĂȂ���Ȃ��v �@�@�@�u����Ȃ��Ƃ��킩��Ȃ��́v �@�@�@�u�i�H�͎��R�I���A���̌��ʂ͎��ȐӔC�v �@�@�@����Ȉꌾ�A�ǂ��l����H ���@���Z���ƌ�A���K�Ј��Ƃ��ďA�E���A�U�O�܂œ�����Ƃɋߑ������ꍇ�̐��U�����́A�j���ŁA��Q���R�T�O�O���~�ɂȂ�B�����ƔK�ٗp�̂܂܂̏ꍇ�͂U�O�܂łŖ�U�T�O�O���~�ŁA���U�����̊i���͂S�{�߂��J���Ă��܂��B �Q�@�u�����Ď��ʎ��v�@�@�����ܕ��Ɂ@�Ζ،���Y ���@�l���̂��ׂĂ͔]�̂Ȃ��ɂ����B�����ł���]�ɁA�ǂ����ĐS�Ƃ������_���ۂ��h��̂��B ���@�������̖��ӎ��͎������̈ӎ����ꐶ�������Ă����݂����Ȃ����炢�́A���܂��܂ȕ�����ʂ��̂������B��������ȊC�Ȃ̂ł͂Ȃ����B ���@�u�F��v�Ƃ����s�ׂ́A�_�̒��ق�j�낤�Ƃ��铮�@�ɂ��ƂÂ��Ă���B �R�@�u���㎍����v�@���̐X���Ɂ@�J��r���Y�E�剪�M ���@���㎍���邢�͐�㎍�́A�P�X�U�O�N��㔼�ɔ����ȕω����o�Ă���B���̕ω��Ƃ́A�������ł��邱�Ƃ̍����������悤�ɂȂ������Ƃł���B�P�X�U�O�N��ȍ~�ɏ�����鎍�́A�^���邱�ƂȂ�������ǂ܂ꂽ"�́h�̎��ォ��A��������ɖ����h�����h�̎���ւ̓]���Ƃ����Ă��������낤�B�E�E�E�n�ӕ��M �@�@�E�P�X�U�P�N�u���͂ق�т��v�@�J���̃G�b�Z�C�@�u�f���m�薽��v ���@���㎍�����܂�ɂ������̎v�z�A�ϔO���邢�͊���̕\���͈͓̔��ɂƂǂ܂낤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ͖�肾�B���̂܂܂̏�Ԃ������Ă����Ƃ����,���͂��������̐l�́A���̎�H�|�i�I�Ȃ��̂ƂȂ��Ă��܂����낤�B���̏ꍇ�ɂ��A��͂葼�҂Ǝ������g���ǂ��������Ɋւ���Ă������Ƃ������ƁA�����ɑ傫�ȃ|�C���g������B�E�E�E�剪�M �S�@�u����W���[�i���v�P�O�����E�P�P�����@�w�� ���@���w�ɂȂ��Č����w�Z�ɂ�����̂́A�n��B�R�~�j�e�B�E�X�N�[���A�w�Z�x���n��{���ƁA���߂���n��Ƃ̘A�g���݂̎{������i����Ă�B���ɂ͂�������ȑ��݂ɂȂ�n���ی�҂������Ɋw�Z�̖����ɂ��邩�A�����Ɋw�Z�̏����͂������Ă���B�E�E�E ����W���[�i���X�g�E�a�c�� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/9 |
�ŋߓǂ{�@�Q�O�O�W�E9�E15�@�L �v [�w�͒ቺ����������{�v�@���t���� �@�@�킪�q�̂܂����������|�I�Ȋw�͂����� �@�@�����ّ�w�����@�A�R�p�j �@�@���͊w�K�يْ��@���́@�� ���@�A�R���ĕ��ɁA��������R�c��ɒ�Ă���A�u���������l�Ԃ̈琬�ɂ́A���ׂĂ̎v�l�����̓y��Ƃ��Ă̊�b�w�͂̑S���ɂ��擾���K�v�B�ߓx�ȉ��I����ւ̔��ȂƂ����ϓ_���牟���i�߂�ꂽ�W�O�N��ȍ~�̋�����v�H�����A��b�b�B�̌y���Ƃ����`�Ŋw�͒ቺ�݁A�����`�̓y���Z�H������B�v�Ƃł��Ȃ�܂��傤���B �Q�@�u����U����{�v��ɂ��āv�@�@��������R�c�� �E�E�E���痧���̎����Ɍ����āE�E�E���\�@�����Q�O�N�S���P�W�� �R�@�u����U����{�v��v�����Ȋw�ȁ@�����Q�O�N�V���P���@����� �S�@�u�h�X�g�G�t�X�L�[�v��Ɨ́@�@���t�V���@�T�R��v ���@�h�X�g�G�t�X�L�[�́u�_�v�̑��݂��߂����āA�L���X�g���̐_�Ƃ������A�Đ_�_�I�ȉF���C���R�̗쐫�Ƃ��Ăً̈��̐_���C���[�W���Ă����悤�Ɏv����B�u���X�R�[���j�R�t�͕������邩�v�̔��f��́A�ЂƂ��ɁA�u�_�ƐG���v�A���Ȃ킿���R�Ƃ̉F���I�Ȍ����������邩�ǂ����ɂ������Ă����B���V�A�̓N�w�҃x���W���[�G�t�́u�_�����R�v�Ƃ̌𗬂��������l�Ԃ̐��_��Ԃ��A�u��n�Ƃ̒f��v�Ƃ������t�ŕ\�����B�����A�u��n�̊��o�v�Ƃ́A����Ӗ��ŁA���O�Ƃ̈�̉��̊��o�ƌĂԂ��Ƃ̂ł�����̂ł���B ���@���̑�n�Ƃ͉����B���́u��n�v�͂��͂�V�A�Ƃ����ŗL�����͂邩�ɒ������Ƃ���ɂ���i���̃g�|�X�i�ʑ��j�Ƃł��ĂԂׂ��ꏊ�ł���B����A�@���A�l����āA���ՓI�ɐl�X�̐S�̂Ȃ��ɂ����n�̗��O�A�Ƃ����Ă悢�̂�������Ȃ��B�E�E�E�E�������������߂��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂́A�����̍��̂Ȃ��̑�n�ł���B���̂�̘������̂āA��n�̂₳�����̂Ȃ��ɂ����ۂ�Ɨn�����킹�邱�Ƃ̂ł���g�́A���̂Ƃ������A�u�Ȃɂ�����m�łƂ��Ă�邬�Ȃ����́v�́A�m���ɐÂ��Ɉ�l�ЂƂ�̍��̂Ȃ��ɍ~��Ă���ƁA�h�X�g�G�t�X�L�[�͌������Ƃ��Ă����B �T�@�u�Y�ꂦ�ʎ��v�킪�����I�@�@�剪�M�@���@ �@�@�@���̐X���Ɂ@�v���� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/8 |
�ŋߓǂ{�@�Q�O�O�W�E8�E10�@�L �v [�]�Ɖ��z�v�@�Ζ،���Y�@�V������ ���@�l�Ԃ̌o���̂����C�v�ʂł��Ȃ����̂��A����̔]�Ȋw�ł́u�N�I���A�v�i���o���j�ƌĂԁB ���@�l�Ԃ̐��_�̗��j�́A���z�̐��E�̊g��̉ߒ��A�ʂ̌�����������A�u���z�̌n���v�ɂ����đ�������B�T�̏��̎q�����E�̂ǂ��ɂ������Ƃ��Ă͑��݂��Ȃ��T���^�N���[�X�̂��Ƃ��v���̂́A���z�̌n���ɘA�Ȃ邱�Ƃł���B���яG�Y���u�ɂ��������������̂��A�a���ȗ��̓��{�́u�u�v�܂�鉼�z�̌n���̒��Ɉʒu�Â����邱�Ƃł���B�l�Ԃ͌����ɂȂ����̂����邱�Ƃɂ���āA���������L���ȃR���e�N�X�g�̉��Ō��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B����ɖL���ȉ��z�̃R���e�N�X�g���ςݏd�˂���ߒ��ŁA���t���a�������B���z�̌n�����ςݏd�˂���Ȃ��ŁA�l�X�͗l�X�Ȃ��̂����z�̐��E�ɑ������B���яG�Y�̏ꍇ�A�����ꂽ�͔̂������|�p�A�؎��Ȑl���̌��ւ̎v���ł������B ���@�����̔]�Ȋw�̒m���ɂ��A���́u���v�͑O���t�𒆐S�Ƃ���_�o�זE�̃l�b�g���[�N�ɂƂ��Ȃ��Đ��ݏo����Ă���炵���B���̐_�o�זE������o���Ĕ|�{�M�̏�ɂ����Ă������ɂ͎��́u���v�͂Ȃ��B�u���́v�]�̒��̈�牭�̐_�o�זE�̊W�����琶����B�������Ȃ�����Ȃ��Ƃ��\�Ȃ̂��A�ߑ�Ȋw�̍ō��ŗǂ̐��ʂ���������Ă��킩��Ȃ��B�E�E�����ӎ��̋N����{���ɗ������悤�Ƃ���A����̎������͂����炭�A������x�f�J���g�̓������ǂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �Q�@�u�v�l�̕⏕���v�@�Ζ،���Y�@�����ܐV�� ���@����̓����u���I�����͎������Ƃ����L���̐��������ƌ����������Ƃ��́A����t�̑R�̌`���Ȃ̂�������Ȃ��B���̑R�̌`���̒�����Ƃ��ɁA�l�ނ̕����̐���������B �R�@�u���{�l�̐��_�Ǝ��{��`�̗ϗ��v�@���~�ɐV�� �@�@�Ζ،���Y�@�u�s�@�g���� ���@���Z��w��ʂ��Ď��͂�����u�{����ҁv�ł������B�₪�āA�l�X�Ȑl���o����ʂ��āA�{��͂��̂܂܂ł͌��݂ɒʂ����A���ɕϗe���Ă����Љ�̂��߂ɂȂ�̂��Ƃ������Ƃ��w�B ���@�v���t�F�b�V���i���Ƃ̓m�[�u���X�E�I�u���[�W���̂��Ƃ��B ���@���{�̑�O�͌������S���Ă��܂���B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/6 |
�ŋߓǂ{�@�Q�O�O�W�E6�E22�@�L �v [���B��Q�̎q�ǂ������v�@���R�o�u�Y�@�u�k�Ќ���V�� ���@���B�ɂ����鎁�i��`�q�j�ƈ炿�i���j �E�E�E����܂ł̉Ȋw�I�����ł́A���|�I�ɐ����w�I�ȑf���̎��d�݂��A���������傫�����Ƃ�������Ă����B���Ƃ��A��s�̂悤�ɁA�킪���ł͊��I�ȗv���Ƃ��čl�����邱�Ƃ��������Ɋւ��Ă��A�����w�I�f���Ɗ����Ƃ��r����ƁA���́A�O�҂̂ق������|�I�ɍ����Ƃ������Ƃ͊��Ɍ��_���o�Ă���B ���@�q�ǂ��s�҂̑�\�I���ǁE�E�E������������Q�Ɖ𗣐���Q�ł���B �E�E�E���ݕی삳�ꂽ��s�Ҏ��̖�W���͉ƒ�ɕ��A���Ă���B�ƒ�ɋA�����Ƃ��D�܂�������Ȃ���Ă���̂ł͂Ȃ��A�s�҂ɂ���ĕی삳���q�ǂ��̐����\�z�ȏ�̐L�т������钆�ŁA�Љ�I�{��̏�͂��łɖ��t��Ԃɂ���A�ی삷��ꏊ���Ȃ�����ۉ��Ȃ��ɉƒ�ɋA���Ă���̂ł���B ���@���ׂĂ̎q�ǂ��ɂƂ��āA���N�Ȉ炿�ɕ��ՓI�ɕK�v�Ȃ��͉̂����Ƃ������Ƃ��l���Ă݂�ƁA�����҂���^������m�芴�Ǝ��Ȏ��g����ގ�������̓�ł͂Ȃ����Ǝv���B �Q�@�u�����̃q���g�E�E���҂����̋���_�v�@�����Ȋw�ȕ� �@�@�@���m�ُo�Ŏ� �@�@�@�R�O�l�̌��҂������b���u�w�сv�̐S����� ���@����ɉȊw���@�E��ɂ͂��Ƃ��b���@������ ���@�F���͎��̑z����₷��^���ÂȂƂ��낾���� �@�@�@�͂��߂Ɍ����肫�Ƃ����Ӗ����킩�����C�������@�@�ї��q ���@���͂�����߂Ȃ���ł��@�����d�����q��Ă� �@�@�@Where there's a will, there's a way. �@�@�@��낤�Ǝv���ł��܂��@�@�A�O�l�X�E�`���� ���@�o��́A���{�l�̂����銴��A�N�w�A�v�z�Ȃǂ��A �@�@�@�������P�V���̒��ɋÏk����Ă�����̂��Ǝv���܂��B�@��܂ǂ� �R�@�u���ׂĂ͉��y���琶�܂��v�@�o�g�o�V���@�Ζ،���Y�@ �@�@�@�]�ƃV���[�x���g ���@���̒��Ɋy�킪���� �S�@�u���䗲�̌��㎍����]�@���䗲�@���̐X���Ɂ@�v���� �@�@�Z�̂̓ǂݕ�,���̓ǂݕ� ���@���̕��@�́A�R�O��̔��Ɂu�Z���^���w�_�v���������Ƃ��ɑ�g�̂Ƃ��낪���܂����B���Ȃ킿���̂���т̍\���I��i�ƌ��āA������Ӗ��ƉC���̗��ʂ��番�͂��悤�Ƃ������̂ł���B�ߔN����Ɏ��o�I�Ȉ�ۂɂ��Ă��l�@����Ƃ����X����������Ă���B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/6 |
�ŋߓǂ{�@�Q�O�O�W�E6�E1�@�L �v [������v�v�@���c�p�T�@��g�V���@ �E�E�E�@��������̊w�Z�Â���E�E�E ���s�s���̐i����Љ�ł́A�w�Z�͒n��̐l�X�ɂƂ��āA�����Ȃ��������̊�Ղł���B �����{�̋���́A��{�I�ɂ͉��ǎ�`�i�Љ��`�̏C���j�̗��ꂩ��v�悳��g�D����Ă����B���x���x���ł͍����ς���Ă��Ȃ��ƍl�����邪�A���x���ł́A�P�X�W�O�N��ȍ~�A�s���`�Ȃ����A�~�ώ�`�i�s���`�̏C���j�̍l���������܂��Ă����B���{�̋��炪�A���܊�H�ɗ����Ă���̂͂��̂��߂ł���B ���w�Z�Đ��̍ŏd�v�ȗv���́A�w�Z�I���̎��R�ɂ���̂ł͂Ȃ��A�C�[�X�g�n�[�����̎��Ⴊ����Ă���悤�ɁA���t�Ɛ��k�͂������A�e��n��̐l�X���܂߂āA���̊w�Z�̍\�������A���������̊w�Z���u�悢�w�Z�v�Ƃ��Ă����Ă����Ƃ������ł��낤�B�I�ꂽ����̊w�Z�����łȂ��A�S�Ă̊w�Z�ɂ��̉ۑ��B������@���ۏႷ�邱�Ƃ��A�d�v�Ȃ��Ƃł��낤�B���Ȃ��Ƃ��`������i�K�܂ł̊w�Z����́A�������{�����Ƃ��ׂ��ł��낤�B �Q�@�u�~�]����]�v�@�Ζ،���Y�@�@�W�p�АV���@ ���l�ԑ��݂̖{�����A���l�̐S���킩��ƌ������ł���B���̓������x����̂́A�]�̑O���t�ɂ���A���l�Ǝ��������̂悤�ɉf�������u�~���[�E�j���[�����v�ƌĂ��_�o�זE�ł���B�~���[�E�j���[�����̏�������āA�������͑��҂����Ƃ��āA�������Ă����B ���@����̎��㐸�_�Ɍ��������Ƃ��A���ɂȂ�T�O�̈�́A�u�q�ǂ��v�ł���B���x�������o�σV�X�e���́B�q�ǂ��̂悤�ɗ~�]���ނ��o���ɂ�������҂̂������K�R������B ���@�������̓��Ȃ�~�]���A�����āA���܂��܂Ȑ��������̒��ő��Â����R���A�l�Ԃ���������v�����ނ��͗y���ɁA�����m���Ɋ�Â��Ă���B�����łȂ���A�n����ł��ꂾ���̒������ԁu�����\�v�ȃV�X�e���Ƃ��đ������邱�Ƃ͕s�\���������Ƃ��낤�B�u���\�]�S�v�́u�����R�v�Ɠ����ł���B�E�E�E�u����̗~�]���m�肷��v�Ƃ������Ƃ�,�u���ȓI�v�Ƃ����j���A���X�������Đ����N�w�I�Ȑ[�݂�悷��ɓ������Ƃ��A�l�ނ͂��̒����T�O��̐i���̊K�i���܂���オ�������ƂɂȂ�̂��낤�B �@�R�@�u���Ǝ��R�v�@�ߌ��r��@�@���̐X���Ɂ@ ���@���ׂĂ̐l���A���ꂼ����ʂ̎��l�ł���[�[�B �@�@�@�������͂Ȃ�ā@����́@�������ɒm�炸 �@�@�@���͎��Ɂ@������Ȃ� �@�@�@�l������ł������ƂɁ@����͎������玩�R�ɂȂ�@ �@�@�@�Â��ɔ���Ă䂭 �@�@�@�����́@�ނ��䂫�@�@�����́@�ʂ̔ނ��䂭 �@�@�@�푈�̂���Ɓ@���Ȃ����@�@���X�̂䂫������C�̂悤�� �S�@�u�b�r�����|�[�g�E�u�����@�U�P�v���ȋ��猤�����@�[�ъ� �E�E�E���U�@���q�ǂ�����Ȃ��E�E�E ���ʊ�� ���ʎx������i�P�j �@�@���@���{����P�N�[�[���̉ۑ�Ɩ��_ �@�@���@���H�I���g�݂p��A(���̂P�j |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/5 |
�ŋߓǂ{�@�Q�O�O�W�E5�E6�@�L �P�@�u��Q��������l����v�@��g�V���@�Ζ؏r�F �����ʎx������́A��Q�̂���c���������k�̎�����Љ�Q���Ɍ�������̓I�Ȏ��g�݂��x������Ƃ������_�ɗ����A�c���������k��l��l�̋���I�j�[�Y��c�����A���̂��Ă�͂����߁A������w�K��̍�������P���͍������邽�߁A�K�Ȏw���y�ѕK�v�Ȏx�����s�����̂ł���B ���܂��A���ʎx������́A����܂ł̓��ꋳ��̑Ώۂ̏�Q�����łȂ��A�m�I�Ȓx��̂Ȃ����B��Q���܂߂āA���ʂȎx����K�v�Ƃ���c���������k���ݐЂ���S�Ă̊w�Z�ɂ����Ď��{�������̂ł����B ��������A���ʎx������́A��Q�̂���c���������k�ւ̋���ɂƂǂ܂炸�A���Q�̗L���₻�̑��̌X�̈Ⴂ��F�����A�l�X�Ȑl�X�����������Ɗ���ł��鋤���Љ�̌`���̊�b�ƂȂ���̂ł���A�킪���̌��y�я����̎Љ�ɂƂ��ďd�v�ȈӖ��������Ă���B �E�E�E�Q�O�O�V�E�S�E�P���ȏȁu���ʎx������̐��i�ɂ��āv���A���̗��O�E�E�E ���{���ɃC���N���[�V�u�Ȋw�Z�́A�{���ɃC���N���[�V�u�ȎЉ�i�����Љ�j�����グ����g�݂Ɛ[���������Ȃ���A�����s�\�ł���B �Q�@�u�N�̂��߂̋���Đ����v�@��g�V���@���c�p�T�� ������͖{���I�ɂ͔͂̍�p�ł��B���犈���͋��t�̎�����I�E�����I��含�̍����A�[���ւ̋����A���邢�͎q�ǂ��Ƌ��t�Ƃ̐l�ԓI�ȐM���W�Ɗw�т����̒��Ŏ����I�Ȋw�K�ӗ~�������Đ��藧�c�݂ł��B �R�@�u�l�ԗ͂̈�ĕ��v�@�W�p�АV���@�x�c�� ���݂�Ȃō��A�����߂��Ȃ������@ �@��P���@�ЂƂ�ЂƂ�̂�邢�Ƃ���ł͂Ȃ��ǂ��Ƃ�������āA���ǂ����܂��傤�I �@��Q���@�N���X�S�����x�������A���͂������F���[�߂܂��傤�I �@��R���@����������āu���₾�v�Ǝv�����Ƃ͂�߂܂��傤�I �@��S���@���₾�Ǝv�����玩���̎v�����͂�����Ɠ`���܂��傤�B�܂��A�搶��F�B�A�Ƒ��Ȃǂɑ��k���܂��傤�I �@��T���@�F�B�������߂��Ă�����A�N���X�݂̂�Ȃ����ӂ��A�����Ă����܂��傤�I �@��U���@�����߂��Ă���l���]�ނƂ��͊w������J���āA�������܂��傤�I �S�@�u�e�̕i�i�v�@�o�g�o�V���@�Ⓦ�����q �T�@�u����ǂށv�@���̐X���Ɂ@�J��r���Y�@�@�@���l�̃R�X�����W�[ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/4 |
�ŋߓǂ{�@�Q�O�O�W�E�S�E�P�Q�@�L �P�@�u���{�̋����v�@�}�g��w�����w�Z�̖��� �@�@�J�쏲�p�ҁ@�}�g��w�����w�Z�������@������ ���@�}�g��w�����w�Z�P�P�Z�͏��������������ʎx������ɂ����āA�ߑ���{�̋�������[�h�������Ă����B���̊����̂��ׂĂ������炩�ɂ���B�E�E�E�E�����ɓ��{�̋���̖���������B �Q�@�u�t�B�������h�Ɋw�ԋ���Ɗw�́v�@����ǐM�E�������Ғ� �@�E�E�����ւ̊w�͂Ɠ��{�̋���@�R�E�E�@���Ώ��X ���t�B�������h�̋���Ɗw�͂̎��̍������\�Ȃ炵�߂Ă���̂́A�i���̂Ȃ��Љ��ڎw���A����������R�ƕ����̐��������A���U�������̂�ǂ����ߊw�ё�����Ƃ��������Љ�̃C�f�I���M�[���瓱���o���ꂽ���{��ɂ����̂ł���B �������i����c��w���_�����A���E���ȏ������Z���^�[���ʌ������j ���t�B�������h�ł́A�w�Z�̋��t�������u�����̘X�C�v�ɂ��Ƃ���`��������B����́A�Èł̒��œ�����Ƃ����A�m�ւƂ����Ȃ��A�l�����݂Ƃ��Ă̊w�Z���t�ւ̑��h�Ƃ�����������߂��\���ł�����B����ǐM�i�k�C�������w�������j �����A�t�B�������h�͐��E�T�ƕ]�����w�͂Ƌ���S�ʂ̐����̍����Ő��E�̍��X���璍�ڂ���Ă���B�����A����͌������u���������v�Ƃ͒������[�[�[����Ӗ��ł͐����́[���₩�ȁu�����̌����v�̐��ʂł�����B�i����ǐM�j �R�@�u�V������������U�w�K�̐U������ɂ��āv �@�@�@�`�m�̏z�^�Љ��ڎw���ā`���\ �@�@�@�����Q�O�N�Q���P�X����������R�c�� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/3 |
�ŋߓǂ{�@�Q�O�O�W�E3�E�Q�Q�@�L �P�@�u�NJ��v�@�g��G�Y�@�A�[�g�f�C�Y ���@�������߉ނɂȂ���@�Ƃ��Ă����ς疱�߂��̂́A���T�̍s�ł��邪�A�NJ��̂���́A��H�̍s�ł������B ���@�l�̎q�̗V�Ԃ��݂�ɂ͂��Â� �@�@�@�����܂Ƃǂ߂��˂� ���@���̗��Ɏ�܂���q����� �@�@�@�V�ԏt���͕�ꂸ�Ƃ��悵 ���@���炿�˂̕ꂪ�����݂ƒ��[�� �@�@�@���n�̓��ׂ��������邩�� ���@���ɂ��ւɂ��͂�ʂ��͍̂r��C�� �@�@�@�ނ��ЂɌ���鍲�n�̓��Ȃ� ���@�V�������ЂƂɌ����C�̏�� �@�@�@�����яo�ł��鍲�n�����R ���@�����Ђ��̊�Ԃ����ӑې��� �@�@�@�������ɂ��͂��݂킽�邩�� ���@����݂̌���҂��Ă��ւ�܂� �@�@�@�R�H�͌I�̂����̑����� ���@�����̒��Ɍ�������O���琢�E �@�@�@�܂����̒��ɖ��Ⴜ�~�� �Q�@�u�����v�@�����ד��@�A�[�g�f�C�Y ���������Ȃ�ӂƂ��ӂ́A���Ȃ��Ȃ�ӂȂ�B���Ȃ��Ȃ�ӂƂ��ӂ́A���Ȃ��킷���Ȃ�B�@�����@�u���@�ᑠ�v�̈�с@�u�������āv��� �����̓��̂���O�ŁA���ۂ̓������Ƃ̒����ɂ��ǂ��̂́A�u�ے�̈�c���@���ꋂ�ސ牭�̐l�v�̑T�̂�����̏C�s�ɂق��Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�@�����ד� �R�@�uCS�����|�[�gVol 60�@���T�@���q�ǂ�����Ȃ��I�v�@�@�[�ъ� �S�@�u���⋳��V���[�YNo�P �V���Ȕ��z�ɂ�鐴�|�����v �@�@�|�����v���@���{����V���� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/2 |
�ŋߓǂ{�@�Q�O�O�W�E2�E10�@�L �P�@�u������x�ǂ݂����@�{���v�@�� �����W�@�t�ƏC���@�� �@�@�킽�����Ƃ������ۂ́@���肳�ꂽ�L�@�𗬓d���� �@�@�ЂƂ̐��Ɩ��ł��B �@�@�i�����铧���ȗH��̕����́j �@�@���i��݂�ȂƂ�������Ɂ@���킵�����킵�����ł��Ȃ��� �@�@�����ɂ��������ɂƂ���Â��� �@�@���ʌ𗬓d���́@�ЂƂ̐��Ɩ��ł��B �@�@�i�Ђ���͂������@���̓d���͎����j �Q�@�u�`���̎Z�����ȏ��@�Ε\���v�@��g���X�@���{�N�v �@�@�E�E�E���쒼���̍l�������ƁE�E�E �����������E�E���쒼�� ���u�q�포�w�Z�p�vS�P�O�N�`S�P�W�N�̍��苳�ȏ��Ҏ[ ���Z�p����̖ړI�E�E�����̐����v�z���J�����A���퐶���𐔗��I�ɐ���������悤�Ɏw�����邱�� �R�@�u������߂���w�͐��E��v�����I���@���c���� �@�@�@�E�E�E�t�B�������h����̐����E�E�E �����ۊw�͒���PISA�iProgramme for International�@Student Assessment�j�Ń_���g�c�̐��E��̍��t�B�������h�BEU�̂Ȃ��ł��o�ϔ��W�D���̂��̍��̒�͂́u�w�́v�ɂ������B���t�B�������h�̊w�Z�͂ł��Ȃ��q�̒�グ�͂��邪�A�ł���q�͕����Ă����B�P�X�W�O�N��A�K�n�x�ʊw���Ґ���p�~���A�����^�̊w���Ґ��ɂ������R�́A��w�͂̃N���X����Ƃ��āA�Ⴂ�Љ�E�o�ϓI�w�i�����A�j�q���k�ō\������Ă�������ł���B ���K�n�x�ʃN���X�Ґ��͂ł��Ȃ��q�̋~�ςɂ͂Ȃ�Ȃ��B �S�@�u�C�ɂȂ�q������L�т���Ɓv�@ �@�@�@���w�ف@�i��T���A���R�b�q �E�E�ELD�EADHD�E�A�X�y���K�[S�A���ׂĂ̎q�ǂ��̌���������ʎx������ �T�@�u����ے�����ɂ����邱��܂ł̐R�c�̂܂Ƃ߁v �E�E�����P�X�N�P�P���V���@��������R�c��A�����������番�ȉ�A����ے����� �U�@�u�c�t���A���w�Z�A���w�Z�A�����w�Z�y�ѓ��ʎx���w�Z�̊w�K�w���v�̓��̉��P�ɂ��āv�E�E�����Q�O�N�P���P�V���@��������R�c��\ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Q�O�O�W/1 |
�ŋߓǂ{�@�Q�O�O�W�E�P�E�V�@�L �P�@�u���̍��̖����ցv�@���a�����@�����ّ�w�����@ �@�@�@�����ܐV���U�S�P�@�E�E�E�����\�Łu�L���v�ȎЉ� ���u�@�����ۏ���������A����ŏ\���ł���v�Ƃ���s���`�҂ɑ��āA�u��R�̓��v�̗���ɂ��ĂA�@����ɉ����āu�\���̕����v�i�^����ꂽ�@��𗘗p������\���̕����j���ۏ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�\���̕����̂��߂ɂ́A������̐����E�[�����s���ł���B�����炪�r�p���Ă���A�P�W�ɓ���܂łɎ����鋳��̎��̊i�����A�e�̕n�x�̊i���Ɉˑ����邱�ƂɂȂ�B���ׂĂ̎q�ǂ������ɓ������ǎ��ȋ���������邱�Ƃ��u�\���̕����v�̕K�v�����ł���B�@��ϓ��Ɖ\���̕��������܂��Ă͂��߂āA���ʕs�����F���邱�Ƃ������������̂ł���B ���Q�P���I�̃L�[���[�h�́u�����\���v�ł���B�Q�O���I�̉Ȋw�Z�p�͌o�ϐ����Ɋ�^���邱�Ƃ��A���̑�P�`�I�����ƐS���Ă����B�����A�Q�P���I�̉Ȋw�Z�p�́u�����\�Ȕ��W�v�Ɋ�^������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B������⎑������˕Ԃ����Ƃ��A�Q�P���I�̉Ȋw�Z�p�ɉۂ���ꂽ�d���C���Ȃ̂ł���B �Q�@�u�����\�ȕ����Љ�v�@�L��ǓT�@��t��w���� �@�@�@�����ܐV���U�O�U�@�E�E�E�u�����ЂƂ̓��{�v�̍\�z�E�E�E ��������{�ɂ����āA�l�̐l���ɂ����鏊��������A���ƁE�n���Ɋׂ郊�X�N�A���邢�́h�Љ�I�X�e�C�^�X�h���ɂ����Ƃ��傫���e�������̂́A���̐l�̎�����Ȃ����w���ł��邾�낤�B�t�Ɍ����A�\���ȁA���邢�͓K�ȋ�����Ă��邱�Ƃ��A���̌�̐l���ɂ����čő�́h�����ۏ�h�Ƃ��ċ@�\����̂ł���A���������Ӗ�������́u�l���O���̎Љ�ۏ�v�̂����Ƃ��d�v�ȗv�f���Ȃ��̂ł���B ���u�����\�ȕ����Љ�v�Ƃ́A�u�l�̐����ۏ�╪�z�̌������\����������A���ꂪ���E��������Ƃ��������Ȃ��璷���ɂ킽���đ����ł���悤�ȎЉ�v�̂��Ƃł���B���ꂪ�o�ϐ������ΓI�ȖڕW�ƍl���Ȃ��A�M�҂�����܂��u���^�Љ�v�ƌĂ�ł����Љ�Ƃ��̂܂d�Ȃ��Ă���B���O�I�ɂ́u�Ɨ������l�v�Ɋ�{�I�ȉ��l��u���Ƃ����_�ł͎��R��`�Ƌ��ʂ����A����ɉ������A�u�������v�Ƃ������l�����āA�Љ�ۏ����ی�Ƃ������_�Ɏ����������ƂƂ��ɁA�l�ƌl���Ȃ��u�V�����R�~���j�e�B�v���u������Ƃ��������t���Ɋ�{�I�ȓ����������̂ł���B �R�@�u����@�m���Ăďd���@�ł���ł�����@���̎����E�E�E�v �@�@��t�E�P�A�}�l�W���[�@����Y�O�i�R���|���j����葡�� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/12/7 |
�ŋߓǂ{ �P�@�u�`�������₢�Ȃ����v�@���c�p�T�@�����ܐV���T�S�R �������{�̋`������͊ԈႢ�Ȃ��A���d��Ȋ�H�ɗ����Ă���B�u�����E���n�����v���d�����A�N�������ʂ���邱�ƂȂ��A�������ɔF�ߍ����A���߂����Ă������Ƃ̂ł���w�Z�ƎЉ�������Ă������Ƃ���̂��A����Ƃ��\�͎�`�Ǝ��R��`�̈ߑ����܂Ƃ����G���[�g��`�E�u���������v�u���҂̘_���v�ɂ���ċ��琧�x�E�Љ�x���ĕ҂��A�����ɐ����鏔�X�̍��ʂ�s������\�͎�`�Ǝ��ȐӔC�_�ɂ���Đ��������悤�Ƃ���̂��A���̊�H�ɗ����Ă���B �������������ɓ˂������Ă���ۑ�́A������\�͎�`�E���ȐӔC�Ȃ���̂�ے肷�邱�Ƃł��Ȃ���A�����E���n���I�E�⊮�I�Ȏw�����O�Ƃ��邱�Ƃɂ�����A���̖\���E���Q���E�ɘa���悤�Ƃ��邱�Ƃł��Ȃ��āA���������Ƌ����������ǂ̂悤�Ȃ��̂Ƃ��đ����邩�A���̗�����K�Ȃ��̂Ƃ��đg�ݍ�����E�Љ�̃��B�W�������\�z���A����𐧓x�v�Ɛ������H�E������H�̎w�����O�Ƃ��Ă������Ƃ��ł��邩�ǂ����Ƃ������Ƃł���B �Q�@�u�w�Z�͒N�̂��̂��v�@�˓c���Y�@�u�k�Ќ���V�� �����w�Z�͎q�ǂ��̂��߂ɂ���B�ی�҂��w�Z��I�ԍő�̊�́A�Z���ȉ����t�W�c�̎��ł���B�E�E�E�w�Z�I�𐫂ɂ��� ���������w�Z�̋��t�Ɛ����Ƃ͎��Ă���B�������̋����E�Ƃł���B�������A�����Ƃ͑I�ׂĂ��A���t��I�Ԃ��Ƃ͂ł��Ȃ��B �R�@�u��㋳��Ŏ���ꂽ���́v�@�X���N�@�V���V�� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/11/25 | �ŋߓǂ{ �P�@�u�l�Ԃ̊W�v�@�ܖ؊��V�@�|�v���� �����l�Ԃ́u�W�v�����ׂĂł���B�����ĉƑ����v�w���܂��u���l�v�ɂȂ邱�Ƃ���o�����邵���Ȃ��B���l���m����͂��܂�u�l�Ԃ̊W�v�B���ꂪ�u������q���g�v�̐�ɂ݂����A�l�Ȃ�́u�����v�ł��B �����T����ʂ��������߂̎O���̃m�[�g�E�E���уm�[�g�E�E���߂��݃m�[�g�E�E�����ƃm�[�g�E�E�E �i���̃m�[�g�͂Ȃ낤�ƍl���܂����B�u����Ȃ�m�[�g�v�ł͂Ȃ����B�h���悤�Ȃ�A�܂��ˁh�Ƃ����m�[�g���낤�Ǝv���܂����B�����āA�c���N���Ȃ炫���Ɓu���ǂ낫���m�[�g�v���낤�Ƃ��v���܂����B�j �Q�@�u�v�z�Ƃ͂Ȃɂ��v�@�g�{����VT�}���F���@�t�H�� �����V���ɂ������Ƃ������Ă��A�܂��n��Ɋ҂��ė��āA���̒n���V�����������Ƃ����̂��{���̏@���ł͂Ȃ����B�E�E�E�e�a���ɂ����Ή����Ɗґ��ł����A���������^���Ƃ��ď@�����l�������B �R�@�u�w�Z�̃����X�^�[�v�@�z�K�N��@�����V�����N�� ������͂�A����͊�{�Ƃ��āA�Љ���\�z���悤�Ƃ���ߑ�O���I�Ȏq�ǂ��i�ЂƁj�̈琬��ڎw���ׂ��ł͂Ȃ����B�������ɁA�����Љ�̕ω������@���G�[�V�����Ƃ��ĉ����Ă����ׂ����낤�B �S�@�u�����̐Ԃ���v�@�����q�Ǎ�@�R�����q�G�@�t���[�x���� �����q�ǂ��Ɍ����������b�E�E�u�Ԃ���͂ЂƂ̖����������A������͂�����Ȃ��E�E�E�v�i�Ԃ���E�E�E1945.3.10.�������P�̂����̏ĈΒe�ƉЁj �T�@�u�q�ǂ��̐S�������₭�Ƃ��v�@�����q�ǁ@�t���[�x���� �����Ǐ��͕s�v�c�ȗ͂������Ă��܂��B�q�ǂ�����ɎƂ߂����S�䂳�Ԃ�ꂽ���t���͂��܂ł��A�S�̕�ɂɋL���Ƃ��ė���Ă���̂ł��B���̋L�����t����ɂȂ�ƁA�ǂ��ƗN���o���Ă���̂ł��B �U�@�u�₳�����J�v�@�����۔V�@KC�N���G�C�e�B�u�@ �����@�����۔V���W �i�������F��̉������җ��ߖڂɎ��W���o���܂����B�u�c��̐���܂ł̂ӂ邳�Ƃ�����v�Ƃ�����|�̏������������Ă��������܂����B�j |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Q�O�O�V/�P�O/�Q�R | �ŋߓǂ{ �P�@�u���c�����Y�v�E�E�����邱�ƂƓN�w�@���c�����@��g�V�� �������{�̖��̎v�z�́u��I�v�ȓ��������B�i�C���h�͒m�I�A�����͍s�I�j��I�����͌`�Ȃ��`�A���Ȃ����ł���B����͎��̂��Ƃ��`�Ȃ�����ł���A�����I�ł���A�����̂��Ƃ����W�I�ł���B����͎�X�Ȃ�`����e����ƂƂ��ɁA�V�Ɉ��̌`��^���s���̂ł���B �Q�@�u�v�z�Ƃ͂Ȃɂ��v�@�g�{����VT�}���F���@�t�H�� ���������ǂ��Ȃ��Ă��A�Љ�ǂ��Ȃ��Ă��@���͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��B�@���̌����͎Љ���ɂ���̂ł͂Ȃ��āA�l�ԑ��݂Ƃ������ɂ���B�l�Ԃ͂����͎��ʂƂ������Ƃ��@���̍ő�̖��E�����ł���Ǝv���B �����@���͐l�Ԑ��_�̎n�����A�������̖��ł���B��Ȃ��Ƃ͏@�����ɂ���B �R�@�u���ɂȂ肽���v�@�����@�����W�@���ю� �����n���̎��l�E�V�c��u���A�l�G�܁X�̎����̎��R��D�荞�D�ꂽ�R��ł��B�i���сj �S�@�u�k�x�U�����������P�����v�@�����V����ޔǁ@�����V���� ���������{�ЉȊw�O���[�v�ɏ������鎄�̒��j�E���ѓN������炢�܂����B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Q�O�O�V�D�X�D27 | �ŋߓǂ{ �P�@�u���̗������v�@���̂��̎��w�@�V��a�]�@�v���� �����������炯�̂�����͂Ƃ��ǂ� �@�@�@�Ђ炪�Ȃ̂����ނ�ɂ������܂� �@�@�@�������������͂��ǂ��������Ă������̂ł� ���������ĂԂ��Ƃ́A�������邱�ƁB�@�����邱�ƁB �@�@�@���ꂾ���ł����A���Ȃ̂ł���B �����U�߂���̂̂��Ȃ����Ɓ@�U�߂�����̂̂��Ȃ����� �@�@�@�ЂƂɂȂ��� �@��l�͂��������Ă���Ƃ������� �@�@�@�ނ��� �@���������Ă��邩�Ɍ����� �@�@�@�M������ϏO�́@�����Ƃǂ��Ȃ��@�͂邩�ȏꏊ���@�@�i�{�N�V���O�j �Q�@�u����̕��@�v�@������w�����@�����w�@�i���j������w����U���� ��������̕��@���w�ڂ��Ƃ�����̂́A��̏��F���Ƃ��ċ����̏o�������Ȏ@���A���Ƃ�n���I�ɍĔF������K�v������܂��B �������݂̓��{�̊w�Z����̍ő�̓����́A�͕�I�l���ƕϗe�I�l���̕���ɂ���B�����̐��x����Ԃɂ�����͕�I�l���Ɨ��z�⓲��Ƃ��Ă̕ϗe�I�l���̕���ł��B���ۓ��{�̎��Ƃ�w�т���������ƁA������؍��̎��Ƃ�w�т����ϗe�I�l���̐��i�������A���Ă̍��X�̎��Ƃ�w�т����͕�I�l���̐��i�����������������Ă���B���̓�̗l���ꂷ�邱�Ƃ͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B����͓��{�̊w�Z����̉ۑ�ł���B �����S���w�̗̈�ł͋����I���Ƌ����I���̂ǂ��炪���Y�����������Ɋւ��鐔�����̌������s���Ă����B���̑命�����A�����I���̌l�w�K�����A�����I���̃O���[�v�w�K�̂ق����A���Y�����������Ƃ𗧏��Ă���B �R�@�u���Ɠ���v�@�֓��씎�@���y�Ё@�l�Ƌ���o�� �������t�͎��Ƃŏ�������B�q�ǂ��͋��t�𗠐�Ȃ��B �����悢���Ƃɂ́A�����ꂽ�|�p��i�Ɠ����悤�ȋْ��ƏW��������B ������i�́u�q�ǂ��v�ł���B ��������͈�̖`���Ȃ̂��B���Ƃ̂Ȃ��ŋ��t���q�ǂ��ƈꏏ�ɖ��m�̐��E�֓˂��i�����Ƃ��āA���̂Ȃ��Ƃ������ނ悤�ɁA�ꂵ�݂������Ȃ���w�͂��ď��߂āA�q�ǂ��ɗ͂����Ă������̂��B �����q�ǂ��͐���������������������A���̗͂��f�����ς��Ă������Ƃ��ł���̂� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Q�O�O�V�D�X�D�R�@ | �ŋߓǂ{ �P�@�u�V�˘_�v�@�Ζ،���Y�@�@�����I���@ �E�E�E�E�E�_�E���B���`�Ɋw�ԁu�����́v�̔錍�E�E�E�E�E �����]�͊w�шˑ��ǂł���B�]�͊w�ё����邱�ƂɊ�т�������悤�ɂł��Ă���B�m�̗~�]�͖����ŁA�ꐶ��������邱�Ƃ�����܂���B�A�C�U�b�N�E�j���[�g���Ɂu�킽��������������ꂽ�̂́A���l�̌��ɏ�������炾�v�Ƃ��������ւ��Ȍ��t������܂��B�u���L���̖͂@���v�u�^���̖@���v�u���ϕ��v�u���̗��q���v�Ƃ������j���[�g���̒B���́A���l���Ȃ킿�ߋ��̐l�X�������������d���Ɋ�Â������̂ł���A�Əq�ׂ��̂ł��B�V�˂́A�[�����炢���Ȃ����I�ȋƐтݏo���Ă���킯�ł͂���܂���B�������g�[�}�X�E�G�W�\�������݂����������Ă���悤�ɁA�ߋ��̂��܂��܂Ȓm���Ɋw�сA�Ō�̂P�p�[�Z���g�̂Ƃ���ŁA�V�̔z�܂̂悤�ȂЂ�߂����l���A�V�˂ƌĂԂ̂ł��B �Q�@�u����R�E�O�@�N��������Đ�����̂��H�v �@�@�{��r�F�~���e�@���@�f�X�J�o�[�g�� �����@����܂ł̊w�Z���琧�x�͂���C���v�b�g�������B���ꂪ�����ċl�ߍ�����Ƃ���ꂽ�킯�ł��B���̌�ɕK�v�Ȃ̂̓A�E�g�v�b�g���Ɩl�͌����Ă����B���ꂽ���̂͏o���B�܂�A�S���Ȃ̕\������I�ĕҐ��ł���B�E�E�{�� ���������Ƃ����̂́A�{���A�������z���f���āA���Ƃ̓Z�C�t�e�B�[�l�b�g��Ƃ������ƂȂ�ł��B�w�Z�͖����◝�z������ł����ė~�����B�E�E���e ������㋳�炪�悭�Ȃ������ƌ�����ő�̗��R�́A���v��ӓ|�������Ƃ������Ƃł��B�E�E���e �R�@�u���^�E���щΎR�v�E�E�b�z�R�ӂ̐������ǂݕ� �@�@�@���c�R�c�̋��S�E�E�k�e�Y�K�@���l�� �E�E�E�u�t�B�v�ł́A�u���m���Ɖ]�ӂ͎��ʂ��Ƃƌ��t������v�����A�b�z�R�͂̕��m���́A�ނ��됶���������Ƃɏd�����������B �������m�Ƃ͐S�f���̂��̂ł���A���m�̈ꕪ�͔����������A���������ʂ��Ƃł���B���̐��_�̔����������邩�炱���A�^���m�̈ꐶ�͈�Ղ̎��Ƃ��Ȃ蓾���̂ł���B �����o�Ƃ��w����킫�ւȂ����ӂ�S������V�ƁA���m������̕��ӂ��킫�ւȂ��A�w�����ɂ����ЁA�����͗����Ȃǂ��������A�F����ƐE��m�炴��V�Ȃ�B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Q�O�O�V�D�W�D�X | �ŋߓǂ�ł�{ �P�@�u���Ƃ͉����v�@�v���Ё@�g�{�����@ �������ɂƂ��Ċm���Ȃ��Ƃ͂��Ƃ����̂Ȃ��Ő��E�𓀂点�錾�t���Â�ꂽ�Ƃ��Ă��A�₪�Ď��͏I���A������̗�N�͏I�������Ƃ������Ƃ��B���������͂��܂ł��I���Ȃ��ŁA���������ֈ�����B�E�E�E���I�Ȕ�g�́A���̉i�v�I�Ȍ����̗}���Ǝ��̈ꎞ�I�ȉ���Ƃ̌��іڂ��Ƃ߂�N�T�r�̂悤�Ȃ��̂ł���B �Q�@�u�����u���v�@�u�k�Ё@���c�@���@ �E�E�E�E�w�т���̓����A�J������̓����E�E�E�E�E �������t�����鋳��T�[�r�X�Ɠ����������悤�Ƃ���ݕ��́u�s���v�ł���B�@ �����w�͂���\�͂ɂ͂͂�����Əo�g�K�w�ɂ�鍷��������B�����g�N���V�[�i�\�͎�`�j���t�F�A�ł���̂́A�u�w�͂��铮�@�t���v�����l�ɕ����ɕ��^����Ă������ɂ����Ăł���B �������X�N�Љ�ł͓��͂ɂ�����킸���ȍ�������ȏo�͍��Ƃ��Č����\���������B���X�N�Љ�ł͓w�͂Ɛ��ʂ̂������̑��֊W������Ă���B���ȐӔC�A���Ȍ���̓��X�N�Љ��҂ɋ��v���鐶�����i�Ƃ�����莀�ɕ��j�Ȃ̂ł��B �R�@�u�w�Z������A�n�������E�E�������E�E�w�ЗZ���̃X�X���v�@���y���� �����s����ψ�����@ ���������s�ł͊w�ЗZ�����w�Z����ƎЉ�炪�d�Ȃ荇���A�q�ǂ�����Ă���������L������ƂƂ��ɁA�q�ǂ�����Ă銈���������������p�v�ƒ�`���Ă���B �����w�ЗZ���ɂ���ĒB�����ׂ��ڕW�͊w�Z�̃X�������ł���B �S�@�u���{�̌���v�z�v�m�g�j�u�b�N�X�@�������� �E�E�E�E�|�X�g���_���Ƃ͉��������̂��B �T�@�u�����Ȋw�Z�̑傫�Ȓ���v�E�E�p�Z�̊�@����E�o���@ �E�E�E�E�E���w�كX�N�E�G�A�@�@�ďC�@��R�����ƒn��U�����l����� �����@���K�͓��F�Z�E�E�E�s���S�悩����w�\�Ƃ���B�w�Z�E�n��E�s�����A�ы��͂��A�������̑����ɓw�߂邱�ƁB�T�N�Ԃ��߂ǂɕ����w������������Ȃ��ꍇ�͓��p�� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Q�O�O�V:/ �V/�P�U |
�ŋߓǂ�ł�{ �P�@�u���Ƃ͉����v�@�v���Ё@�g�{�����@ �������ɂƂ��Ċm���Ȃ��Ƃ͂��Ƃ����̂Ȃ��Ő��E�𓀂点�錾�t���Â�ꂽ�Ƃ��Ă��A�₪�Ď��͏I���A������̗�N�͏I�������Ƃ������Ƃ��B���������͂��܂ł��I���Ȃ��ŁA���������ֈ�����B�E�E�E���I�Ȕ�g�́A���̉i�v�I�Ȍ����̗}���Ǝ��̈ꎞ�I�ȉ���Ƃ̌��іڂ��Ƃ߂�N�T�r�̂悤�Ȃ��̂ł���B �Q�@�u�Z���搶�ɂȂ낤�v�@���o�a�o�Ё@�����a�� �@�@�����旧�a�c���w�Z�� �����}�l�W�����g�̗ǂ����������A������v���^�Ɏq�ǂ������̂��߂ɂȂ邩�ǂ����̌��ɂȂ�̂��B�Ȃ��q�ǂ��������u������낤�Ƃ��Ȃ��Z���v�̒Ⴋ�ɍ��킹�āA�������]���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B ����������̐M��������ɂ́A�Z���̃��[�_�[�V�b�v�ɗ�����ꂽ�w�Z�̊J���ƒn��Љ�̍Đ��ł����Ȃ��B �����Đ����ׂ��͋���ł͂Ȃ��āA�n��Љ�Ƃ����ł�����ǎ��̃R�~���j�P�[�V�����Ȃ̂ł���B �R�@�u�C���h���b�Z�p�v�@���{���Əo�ŎЁ@�v���f�B�[�v�E�N�}�[�� �S�@�u�c�������̐��U�v�@���z�Ɂ@�ԑ��x�m�j �T�@�u����Đ���c��P���E��Q���v �@�@�Љ������ŋ���Đ��� �U�@�u�b�r�����|�[�g�@�u�n�k�T�X�@�v���W�@�Љ�U �@�@���@�q�ǂ�����Ȃ��I�@�[�ъ� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Q�O�O�V/ �U/�P�O |
�ŋߓǂ{ �P�@�u���������v�@�v���Ё@���̐X���Ɂ@�J��r���Y �������͐l�Ԃ̐����̍ł������I�ȂƂ���ňꌩ��l�ԓI�Ɍ�����قǂ̐[���ɂ����Đl�X�̂��̂ɂȂ�Ȃ���Ȃ�ʁB �Q�@�u�����l����v�@�v���Ё@���̐X���Ɂ@�J��r���Y �����͂��߂ɒ��ق��������B���t�͂��̂��Ƃł����B���ق͐l�Ԃ̓G���B���������ɒ��ق͕�ł���B�����݂͂Ȓ��ق��琶�܂ꂽ�B �����ڂ����x�[�g�[�x������銴���͏�ɂЂƂ̂��̂Ɍ����Ă����B�h�ڂ��͐�������B�h�����̊������ڂ��͂��̂悤�Ɍ��t�ɂ��邱�Ƃ����o���Ȃ������B �R�@�u��l���G�{�ɗ܂���Ƃ��v�@���}�Ё@���c�M�j �������̐��ɐ��܂�ł������͗r���̒��̈��S�����炷���ɒE���o����킯�ł͂Ȃ��B��e�ɕ������߂��邱�Ƃ��A����Ηr���ɑւ����̂Ƃ��ċ��߂�B�S�̔��B�̂��߂ɂ́A�������������W�����Ȃ��Ƃ��R�Ύ��܂ł͕K�v���Ƃ����B �h�S�̕��͂R�N������B�h�E�E�n�Ӌv�q�@�c����w��w�������ȍu�t |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/4/24 |
�ŋߓǂ{�@2007/�S/�Q�S�@�L �P�@�u���x��������̔����v�@�_���ҏW���ҁ@�����I���V�X�U �@�@�@�E�E�E�A�W�A�E�����E�X���E�E�E ���@�s��̌��ʐӔC���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��l������_�ɂ���̂͂������Ȃ��̂��B�E�E�E �㓡�c�����i�́E�����Ɓj ���@���q���ɂ��l���̌����ƍ���ɂ��o�ϐ����Nj�����͕s�\�ɂȂ����B����т��Ă����o�ϒ��S�I�v�l�̓]���́A���鍑�̕����I�`���ɍ��������̂ł���A���o�ςւ̈ڍs�͒����I�ȃv���O�����Ɋ�Â������I�Ȑ����헪��K�v�Ƃ���B�`���I�Ȕ��ӎ��A���R���ւ̑@�ׂȔz���A�M���⒲�a���L�[���[�h�Ƃ����l�ԊW�A���Ȏ咣��������������Ƃ��铹���ρA�����ɍ���������ς�A�_�����炭�鏃�����A�I�Ȓ����ϔO�Ȃǂ�w�i�Ƃ����ϗ��I���_�A�������`���d��u�`�̐��_�v�A�A�����J�����̍��w�r���Ƃ͑ɂɂ��鎿�f�Ŏ��R�ƒ��a������w�̓`���I�Ȗؑ����z���A�i��������j�ςł͂Ȃ��h�͐����̗��j�ρA�����͓��{�̐��_�����̊j���`�����̂ł������B�u�悫�Љ�v�͂����ꂱ���̉��l�ς̍Ĕ����Ƃ��̋�̉����܂ނ��̂łȂ���Ȃ�Ȃ����낤�B�E�E�E�����[�v�i���s�勳���j |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/�S/�W | �ŋߓǂ{ �P ���{�Ƃ������@�@���������@�m�g�j�u�b�N�X�P�O�U�V �@�E�E�E�E���������E���낢�̕����E�E�E�E �Q�@���Ǝ��R�@�ߌ��r��@���̐X���Ɂ@�v���� �@�@�E�E�E�E���Ɗv���E�E�E�E �R�@���C�Ҍ��C�̎�����i�����w�Z�j�@ �@�@�@�Ȗ،�����ψ���E�Ȗ،���������Z���^�[ �S�@�L�O�u���@�u�S�̋���Ə@���v�@�������ю�@��c�F�M �@�@�l�Ԃ͑厩�R�ɏh�肵�Ă��� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/3/21 | �ŋߓǂ{�@�i�Q���P�S���`�j �P�@�V��������̋��E�����@�H�c�����E�����w�@�L��t�A���} ���@���t�̎d���́A�w���Ɏ���̐S�I�G�l���M�[�������ނ��ƂŁA�X�l�̐��k�Ɍ����āA��]�𓊎����邱�Ƃ��B ���@���t�͐��U��ʂ��ċ��t�ɂȂ�B �Q�@���f�B�A��@�@���q���@�A���h�����[�E�f���B�b�g�@NHK�u�b�N�X ���@�Љ�����n�߂Ă���B�E�E�E�����A�\�����Ă���d�Ԃ̒��ɂ���ƁC�N�����̓d�Ԃ��\�����Ă���ȂǂƂ͎v��Ȃ��悤�ɁA���̎Љ�\�����n�߂Ă���A���̐�ɔߎS�Ȍ��ʂ��҂��Ă��邱�Ƃɐl�X�͋C�Â��Ă��Ȃ��悤���B���f�B�A�́A���������\����H���~�߂悤�Ƃ��Ȃ����肩�A�J�[�u�ł܂��܂��X�s�[�h���グ��悤�ɐ����Ă���B ���@�\���Ȓm���ɗ��ł����ꂽ��O�̈ӌ����琬���A����𐭍�ߒ��ɒ��ڔ��f�����邽�߂̎d�g�݂́A���f�B�A���ꎩ�̂���͌����Đ��ݏo����Ȃ��ƍl�����ق����K���낤�B����䂦���Ȃ��Ƃ���̎�i�Ƃ��̌������K�v�ɂȂ�B���f�B�A�����ɂ˂ɉ��^�I�ɐڂ���ᔻ�I�v�l����Ă邽�߂ɁA���f�B�A���e���V�[�̋���𐧓x�����Ă������Ƃł���B���ɁA�����I�����v���鐭���̈��g�߂ȂƂ���ɗ��Ƃ��Ă䂭�����I�Ȏd�g�݂��K�v�ɂȂ�B����ւ̒��ړI�Q�����\�ɂȂ��Ă͂��߂ē��c�I�����`���������ꂤ�邩��ł���B �R�@���I�����`�@���R�C�i�@���̐X���Ɂi�v���Ёj ���@�����͂��߂Đ�㎍�Əo������Ƃ��A��㎍�͑啪�����тꂽ������Ă����B�E�E�E�@�u�r�n�v�^���̒��Ɏ����������̂́A�u�����ɐ����ׂ����v�Ƃ����v�z�ł͂Ȃ��āA�u�����Ɏ��ʂׂ����v�Ƃ����V�j�V�Y���̉e�ł������B ���@���R�͌����Ȉ���̎��W�ł���Ƃ������Ƃ��A��������q�ǂ��͂Ђ����ɒm���Ă���B ���@�ԂƂ����������Ƃ������Ɏ��Ă������Ƃ���A�Ȃ�ƂȂ����Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ₢�����������肷�鏭�N�����Ă��Ȃ����Ƃ͂Ȃ����낤�B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/�Q/14 | �ŋߓǂ{ �P�@������v���f�U�C�������@�����@�w�@��g���X ���@�ǂ̍��̃J���L���������{���I���e���J��Ԃ��o�ꂷ��u�����^�J���L�������v���̗p���Ă���B�ςݏグ�^�ł́A���Ƃ����e�����ՂɂȂ��Ă��A�q�ǂ����炪�{���I�T�O�𒆐S�ɒm�����֘A�t���\���t���Ċw�Ԃ��Ƃ�����ɂȂ�A�ËL��`�̊w�тւƌX���Ă��܂��B ���@���t�͋��Ȃ̐��Ƃł���ȏ�ɁA����̐��Ƃł���ׂ����B �Q�@������v�̂䂭���@���c�p�T�@��g�u�b�N���b�g�@�m�n�@�U�U�W ���@�w�Z����̒��S�I�Ȗ����́A�����̓`�B�A�w�͂̌`���A�l�ނ̈琬�ł���B ���@�����̃v���W�F�N�g�Ƃ��Ă̋�����x��������̂́A���E���Ɖƒ��n��Љ�̐M���E�x���E���͂ł��B���̋��E���̐�含�E�������ƌւ�E�����ɂ��Ȃ��Љ�̋���͎��s���܂� �R�@������@�V���F�@��g�V���@�@�����搶�Ƃ͂ǂ������l�� �S�@�w�Z�̒����@�����w�@���w�ف@�w�т̋����̂�n�� �T�@�w�т��瓦������q�ǂ������@�����w�@ �@�@�@��g�u�b�N���b�g�@�m�n�@�T�Q�S �U�@�w�͂�₢�����@�����w�@ �@�@�@��g�u�b�N���b�g�@�m�n�@�T�S�W �V�@�w�͒ቺ�̎����@���J���F�A�u���G�g�A�����r���A���c�T�q �@�@�@��g�u�b�N���b�g�@�m�n�@�T�V�W �W�@��O����Љ�̂䂭���@���J���F�@�����V�� �X�@�����Љ��@�O�Y�W�@�����АV�� �P�O�@CS�����|�[�gVol�@�T�R�C�T�S �@�@�i�m���Ȋw�͌���Ɍ����ćT�C�U�j�[�ъ� �P�P�@CS�����|�[�gVol�@�T�T�C�T�U�C�T�V �@�@�i���q�ǂ�����Ȃ��@�T�A�U�A�V�j�[�ъ� �P�Q�@�^�������Ɩ����搶�@��������q�@�钹�� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/1/3 | �ŋߓǂ{ 1�@�F�����@����F�T�@���ԏ��X *�@���̎���̉Ȋw�҂��A�F���͂Ȃ�����Ȃɂ��������̂��Ƃ������Q�Ƌ^�₩�瓦����Ȃ������B�F�����Ȃ�����قǂ܂łɐ��R���钁����ۂ��A���ړI�I�ɂ����Ă���̂��B�F�����x�z���镨���@�����{�萔�́A�Ȃ����������w�I�Ȃ̂��B�d�͒萔�́A���̉F���������ݏo���C��݁A�i�������Đl�Ԃ̑��݂ւƓ�����ł���ȊO�ɂ͂Ȃ��Ƃ����œK�̑傫���ɒ�܂��Ă���B����́A���R�ƌĂԂɂ��Ă��m���I�ɂ��肦�Ȃ��悤�ȋ��R�Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B ���@�Ȋw�����炩�ɂł���̂́A�F���ɂ�����l�Ԃ̈ʒu�ƕ����I���ݗ��R�����ł���B���̂悤�ȉȊw�̌��E���āu��X�Ƃ͉����H�v�Ƃ����l�ԑ��݂̖{����₤�̂ł���A�Ȋw�͔ۉ��Ȃ��N�w�̗̈�ɑ��ݓ���Ă�������Ȃ��Ȃ�B���ł��邩�ł͂Ȃ��A�Ȃ��Ɣ�����l�Ԍ����͉Ȋw���Ăѐl�Ԃ̖��ɗ����߂����ɂȂ肤��B����͉Ȋw�̖��Ƃ������Ȋw�҂̖��ł���B �Q�@�{��x�́u�[�݁v���@�����w�@���}�АV�� ���@�P�O�Ƃ����͎̂����������܂ł������Ă���u�q�ǂ��Ƃ����[�݁v�̂��ƁB���q�ǂ��Ƃ����[�݁����C���W�����O�����̂̐_�����̂��̍Đ�����Ƃ��끄 �R�@�Ǐ�����͂��܂��@���c�G�@�m�g�j���C�u�����[ ���@���t�͐l�Ԃ̎q�ǂ��ł͂Ȃ��A�l�Ԃ����t�̎q�ǂ��ł��B��Ȃ���̂Ƃ͎��������܂��������t�̂��Ƃł��B �S�@�i���Љ��@�k�؏r�ف@��g�V�� ���@���{�̎Љ�͂��܊K�w�Œ艻�Ɍ������Ă���B�n���҂̑���͎Љ�ɂƂ��ă}�C�i�X�ł��荑�Ƃ̏������낤������B�������ƌ������͗��������˂Ȃ�Ȃ��B 5�@���щΎR�@�����@�V���� 6�@���E�\�h�@�����˗F�@��g�V�� ���@���E�͎��R�ӎu�ɂ��ƂÂ��đI�����ꂽ���Ȃǂł͂Ȃ��A����u�������ꂽ���v�ł���Ƃ����̂����_�Ȉ�Ƃ��Ă̎��̎����ł���B ���Q�O�O�T�N�x�@�����v���@ ���E�ɂR�Q�T�T�Q�l�A��ʎ��̎��҂U�W�V�P�l |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/12/3 | �ŋߓǂ{
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/11/06 |
�� �Ζ،���Y�u�S�ݏo���]�̃V�X�e���v�m�g�j�u�b�N�X ���`����i�����E�E�E�r�����������@�r���������������E�E�E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Q�O�O�U/10/15 | ���@�ŋߓǂ{ �P�@�q��ĕS�ȁu��闝�R�͎��ɂ������v : �q���ȂȂ��@KSS �Q�@�u�v�z�Ƃ��Ă̑S���������v�@����C���@�����ܐV�� �R�@�u����̗͂����߂��v�@���|�t�H�P�P���Վ������� �S�@�u�n���E�F���E�����Đl���v�@���ԏ��X�@����F�T �T�@�u�����̎�����v�@�o��L�V�@WAC �E�E�E�l�b�g���[�N�Љ�̉��S�́E���S�́E�E�E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/9/25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/9/18 | �ŋߓǂ{ �P�@�u�w�͂̐V�������[���v�@�A�R�p�j �@�L���������s���y�����w�Z�Z���@���|�t�H �������@���Q���N������тƊ�b��{�̓O�ꔽ���̌��ʂ́A�ی�҂Ƃ̘A�g�����܂������A���҂𗠐邱�ƂȂ��q�ǂ������̊w�͂����߂邱�Ƃ��\�ɂȂ�B �Q�@�u���炾��h���Ԃ�p������v�@�V���@�F�@�p�쏑�X �������@Moving English�[�@���炾��h�蓮�����Ȃ���p����N�ǂ��邱�ƂŁA�u���{��̐g�́v����A�u�p��̐g�́v�ւ̃��[�h�`�F���W���Z�Ƃ��Đg�ɒ����悤�B �R�@�u�����v�@�����@�w�@�����ܐV�� �������@���͐l�Ɛl�Ƃ̂������̒��ŁC���N���鎖�ԂƂ݂�ׂ��ł���A�Ǐ�Ƃ��ĂƂ炦��ׂ��ł͂Ȃ��B���V�M�u���ǂƂ͉����v �������@�m�b�x��̖����l�̕a���Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�ޓI�ȋK�͂ł̎��R���ۂƂ��Ď~�߁A���̌��ۂȂ����Ă͐��������Ȃ��ޓI�����̑��̂𗝉�����ؓ����A�����Ǝ�ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�E�E�E���I���_�a���@Asperger�@�͕a�C�ł͂Ȃ��B�����@�w �S�@�u������Ƒ҂��āI�l���������v�@�a�c����@����o�Ŏ� �������l������ŏd�v�Ȃ̂́A�u�l�͂����Ȃ鑮���������Ă��Ă����ʂ���Ȃ��v�Ƃ������@��P�S���̐l�������ɂ��Ƃ����āA�}�C�i�X�ɕ]������Ă��鑮���𐳓��ɕ]�����Ă������Ƃł��B �T�@�u�|�����v�@���R�G�O�Y�@ �������@�g�C�������Ƃ͐S�����Ƃ��B �U�@�u���䋳���̓�����u�`�^�v�@����F�T�@�W�p�АV���@�@ �V�@�u�F���l�Ƃ��Ă̐������v�@����F�T�@��g�V�� �W�@�u�ꖜ�N�ڂ̐l�Ԍ��v�@����F�T�@WAC �������@�ꖜ�N�O�̋C��ϓ��ɍۂ��āA��X�͔_�k�q�{���n�߂��B����͒n���w�I�ɂ̓q�g�����������番����A�l�Ԍ��������Đ�����Ƃ����I�����������ƈӖ�����B�ȗ���X�́A�������т邽�߂����̑��݂ł͂Ȃ��A�Ȃ����݂���̂��A���炻�̑��ݗ��R��₤���݂ɂȂ����B��X�͉F����F�����邽�߂ɐ��܂�Ă����Ƃ����邩������Ȃ��B�������Ƃ���ƁA�����F����������Ƃ�������́A��X�����̑��ݗ��R�������A���������ĕ����̖��ɒ��ʂ���̂́A�����̃p���h�b�N�X�Ƃ������A�K�R�Ƃ����ӂ��ɂ��l������B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/8/8 | ���@�ŋߓǂ{ �P�@�u�L����q�ǂ��͐H���ŕς���v�@�Ғ��@��t�O���j�@��o�Ŏ� ���@�H��ʂ��̂ƐQ�ʂ��͖̂��ɗ����ʁB ���@�Ƒ��̌��_�͋��H�ɂ���B�H�̕���͉Ƒ��̕���B �Q�@�u������{�l�v�@���c�M�j���@�V���Ёi�ēǁj �R�@�u�Q�[���]�̋��|�v�@�X���Y���@�����l�V���@NHK�o�� ���@�Q�[�����̔]�g�͒s���Ɠ����B ���@�l�Ԃ炵���͑O���O��ɂ���B ���@�L����Ƃ������ۂ͓����]�i��]�Ӊ��n�j�̍s����}���ł��Ȃ�����N����B ���@�ŋߖ��ɂȂ��Ă���ADHD(���ӌ��ב�����Q�j�͏W���͂��ቺ���A�����������Ȃ����Ƃ������ł��B���̏�Q�̂���q�ǂ������̔]�ׂĂ݂�ƑO���O��A�я��O���Ȃǂ̃j���[�����������ቺ���Ă��邱�Ƃ��m���Ă��܂��B �S�@�}���K�u�ΐ����v�@������� �T�@�}���K�u�{���v�@������� �U�@�u�w�͂���Ă��v�@�u���G�g���@��g�V�� ���@�w�͌`���̖��ɂƂ��Č���I�Ȃ��Ƃ́A�u�K���Â��v�̖��ł���B���Q�� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Q�O�O�U�E�V | �ŋߓǂ{ �P�@�u�{�����ʂƂ���\�͂����܂���v�@Barry�@Sanders �V�j�� ���@Violence,Electoronic Media , �@�@ and the Silencing of the Written Word �@ �@America'sYouth is dying not to read. �Q�@�u�l�ԂɂȂ�Ȃ��q�ǂ������v�@����P��@���i�����j�o�Ŏ� ���@�q�ǂ����̂ƐS����Ă�ׂ��u�q�����v�ɁA�����ɕ��������Đl�ƌ��t�����킳���ɁA�����Ԃ��߂����Ƃ������ƂȂǒ����l�ނ̗��j�ł��ĂȂ��������Ƃł���B ���@���͂�ƒ�ɋ���͂ȂǂȂ��B�������e������܂߂����f�B�A�E���e���V�[���炪�K�v���B �R�@�u���Ȃ�Փ��E�E�����E�����J�R�@������l�v�@�������q�@���z�� �S�@�u�_���@����Ƃ͉����v�@���]���E�����E����E���{�@���t�V�� ���@�l����̂ɂ������j�b�g�́A�r�b�O�o���Ɠ�����Ԃō��ׁA�������ł���B�Q�O���I�͂��ꂪ���z���Ƃ��Ă���Ă������A�Q�P���I������ł�낤�Ƃ���Ƃ����ɔj�]����B���A�n��ł��������A�����ł͌��t���@��̋��S�͂Ƃ��ē����Ă���B����Ƃ������͍̂��Ƃ��������̂̋��S�͂��̂��̂ŁA����������邱�Ƃ������ɏd�v�Ȃ��Ƃ��B���������j���N�w�����̕������������肵�Ȃ��ƌ��ǂ��߂ł���B ���@�Q�O���I�I�Ȃ��낢��Ȃ��̂͐l�Ԓ��S��`�ŁA�l�ԂƂ����m�I�����̂𑊑ΓI�Ɍ��Ă��Ȃ��B�l�Ԃ𑊑ΓI�Ɍ��鎋�_�ŁA�Q�P���I�ɂ͂ǂ������������z�����邩���u��̏�̉_�v�ł��傤�B �i����F�T�j �T�@�u���c�u���P�X�U�W�|�P�X�U�X�v�@���O�@�����V�� ���@�C������ē����ł���悤�ɐl�g������āA�@���̖����̗E�m�����̒ʂ蓹���J���ꂽ�B ���@�N���܂��o���Ă��� �@���̂悤�ɂł͂Ȃ��@�@�@�ӂ邦�Ȃ��玀�ʂ̂��@�@�ꌎ�͂���Ȃɂ��������@ �@�@�@�B��̖��S�Œʉ߂���Ă���̂��@�@���������Ă������̂� ���@�A�т����߂ČǗ������ꂸ �@�͋y�����ē|��邱�Ƃ͎����Ȃ����@�͐s���������č����邱�Ƃ����ۂ��� ���@�@��������ƐM���ė��鉮��Ɋ��ƂȂ�܂ŗ��������ׂ��@�@�@�@���Y��s�q |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Q�O�O�U�E�U�E�T | ���ŋߓǂ{ �P�@�u�v�t���̊�@���ǂ��݂邩�v�@���ؒ����@��g�V�� �Q�@�u�q�ǂ��̔]����Ȃ��v�@�@�@�@�����́@PHP�V�� �R�@�u�j�[�g�@NEET�v�@�@�@�@�@�@�@�@���c�L�j�E�ȏ����b�@���~�� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Q�O�O�U�E�T�E�U�@�@ | ���ŋߓǂ{ �@�@�u�ǐS�̎��R�Ǝq�ǂ������v�@�@�������j���@��g�V�� ���@��P�X���@�v�z�y�їǐS�̎��R�́A�����N���Ă͂Ȃ�Ȃ��B �����������������Ƃ��C�v�z�ǐS�̎��R��ۏႷ��Ƃ������Ƃ́A��{�I�ɓ����I�A�v�z�I�u�������v�̔��f�ɍ��ƂƂ��Ċւ��Ȃ��p�����Ӗ�����B ���������Ƃ�w�Z�́A�q�ǂ��̓����I���f�\�͂���Ă�̂ɁA�ŏI�I�ȐӔC�������Ƃ͂ł��Ȃ��B�E�E�E�q�ǂ��̓����ӎ��̔��B�̒��S�I�Ȗ�����S���͎̂q�ǂ��𐢂ɑ���o�����e�ł���B �������v�z�ǐS���l�̐l�i�̊j�S�ɂ�����̂Ƃ��Č��͂ɂ��N�Q����ׂ��łȂ��̂́A���S����邱�Ǝ��̂��������ł��A�v�z�ǐS�������Ɍ��ׂ��łȂ����I�����Ƃ��ă^�u�[�����邱�ƂɈӖ������邩��ł��Ȃ��B���@�ɂ��v�z�ǐS�̎��R�̕ۏႪ�K�v�Ȃ̂́A�v�z�ǐS���l�̎������x���錮�Ƃ��Ă̖������ʂ�������ł���B�E�E�E��{�I�l���Ƃ́A�����炵�������Ă��������ł���B�i���̐V���͋v���Ԃ�Ƀ������Ƃ�Ȃ���Q��ǂB�j |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
��������R�c��\�@�Q�O�O�T�E�P�O�E�Q�U�u�V��������̋`�������n������v��� |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Q�O�O�U�E�Q�E�Q�V | ���ŋߓǂ{ �֓��F�@���u�q�ǂ��ɓ`�������O�̗́v���@�m�g�j�u�b�N�X �X�|�[�c�̏�B�ɂ����āA��b�I�Z�p�̔������K���y������w���҂͂��Ȃ��B���R�őn�������ӂ��v���C���A��{�̔������K�Ɏx�����Ă��邱�Ƃ́A�����̗��ł���B�������A�w�͂̌���Ƃ����i�ɂȂ�ƁA���̓�����O�̑O���L����Ȃ��Ȃ�B �E�E�E�w�Z����̍ő�̒����͋����͂�����Ƃ������Ƃł���B�|���Z�̋��͋�������Ȃ���Ύ��R�Ɋo��������̂ł͂Ȃ��B���������g���[�j���O�͊w�Z�Ƃ����ꏊ�ɂ����Ă���B�w�Z���g���[�j���O���y������悤�ɂȂ�A�w�Z�̎Љ�I���݈Ӌ`�͂��悢��ቺ���邱�ƂɂȂ�B�@ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Q�O�O�U�E�Q�E�P�T | ���ŋߓǂ{ �@�K�q�q�Y���u�����̓N�w�v���@�m�g�j�u�b�N�X �a�̂ɑ��鐼�s�̎����́C���S�ւ̕��ցB���Ȃ킿�����I���i�ւ̎�i�ł������B�E�E�E�����̊����͎�ş��ς̂Ȃ������A���̐������E�ł̎��H�̂Ȃ��ɂ���B �E�E�E�a�̑��^���E�E�E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Q�O�O�S�E�P�O�D�R |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||