
弘法独鈷水<加園>
P2
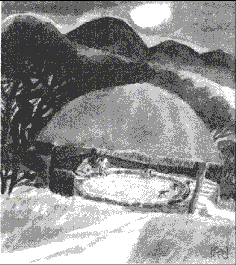 「お坊さん、ちょっと待ちなや、おらが汲んできて来てやっから。」
「お坊さん、ちょっと待ちなや、おらが汲んできて来てやっから。」
と、山を下りて行った男は、しばらくして汗をふきふき戻ってくると、竹筒を差し出した。
お坊さんは、
「おお、ここは水もうまいし、眺めもいいところだ・・・・・」
と、満足そうに川向こうに広がる加園の村里を見やりながらつぶやいた。
「でもなあ、ここは水の便がわるいのが苦労の種でやんして・・・・」
男の話すのを聞いたお坊さんは、
「よし、それでは・・・・」
と、持っていた独鈷を足元につきさして、何やら唱え始めたが、やがて
「ええっ!」
と、するどい声とともに独鈷を引き抜いた。と同時に、水がほとばしるように湧き出してきた。
「おお、水、水、水だ。」
と、湧き出る水を飲んだ男は、不思議な力がでて、仕事も一気にはかどったという。
このできごとは、村中にひろまった。村の人たちは、お坊さんのことをあれこれうわさし合ったが、だれもその名を知らなかった。
そののちしばらくして、通りかかった旅の人がその話を聞いて、
「そのお坊さまは弘法大師さまにちがいない。大師さまは空海といって、ご在世中、
全国をおまわりになり、困っている人々をお助けになったえらいお坊さまです。」
と、弘法大師についての話をしていった。それで、村の人たちはこの泉の水を「弘法独鈷水」というようになったという。
弘法独鈷水の湧き出る泉の近くに、明治時代の始めのころまで、宝蔵院という真言宗の大きな寺があった。
この寺がいつ頃できたかははっきりしないが、言い伝えによると、弘法二世の
開基といわれ、昔は大勢のお坊さんがいて、かなり栄えたこともあったという。
弘法二世は、この独鈷水を用いて、九尺二間のわら屋根の湯場をつくった。
この湯に入ると、長生きするばかりでなく、いろいろな御利益があるというので、
村人ばかりでなく、遠くから湯治に来る人もあった。
その頃のことであろうか、この寺に力自慢の作男がいた。ある時、寺の奉納相撲の
勝ち抜き合戦に出た作男は、出てくる相手を次々と投げ倒していった。あまりの
強さに立ち向かう者もなくなり、作男の優勝が決まりそうになった時である。
つづき
|

